『資本論』は大量消費時代の前に書かれている
「賢明な消費は、賢明な生産よりもずっと困難なわざである。」
ジョン・ラスキン『この最後の者にも』(1860年)
消費社会において個々の消費者は群衆の中に埋没したのか、私たちの消費体験は幻影に過ぎないのか、前回提起した問いについて、今回は消費文化や消費主義の台頭がいかに論じられてきたのかに注目しながら考えてみたい。これは、冒頭のラスキンの言葉にある「賢明な消費」とはいかなるものか、また果たしてそのようなものは存在するのかを問うものでもある。
冒頭の一節は、イギリス人批評家ジョン・ラスキン(1819–1900年)が1860年に発表した論文「この最後の者にも」からの引用である(1862年、同名の書籍として出版)。美術評論家としても知られるラスキンは、政治経済に関する著作も多く、特に本論文(書籍)は、後にインドの民主運動家マハトマ・ガンディーにも大きな影響を与えたと言われている。本書でラスキンは、18・19世紀の経済学者や経済学に対する批判を展開し、国家経済のあり方、特にあるべき生産活動やその目的について論じている。ラスキンは、以前触れたカール・マルクス(1818–1883年)と同時代人である。ラスキンとマルクスが『この最後の者にも』や『資本論』(1867年)を出したのは、技術革新や工業化による大量生産体制に伴い経済構造が変化していくちょうど過渡期にあたる。つまり両者の考察は、その後本格化する大量消費時代よりも前のものだということになる。
「生産というのは苦労してものをつくることではなく、有益に消費されるものをつくること」
ここで注目したいのは、マルクスとラスキンが論じる生産と消費の関係である。マルクスは、生産活動(工場生産)にその分析の主眼を置いて、資本主義システムとその社会について論じた。一方ラスキンの論には、生産に注目しながらも、消費のあり方についての議論がより明確に現れているといえるだろう。「生産というのは苦労してものをつくることではなく、有益に消費されるものをつくること」だと論じるラスキンにとって、消費は「生産の目的」であり、人が生きるために行われるものとなる。そして、究極的に「国家の問題は、国家がいかに多くの労働を雇用するかということではなくて、いかに多くの生をつくりだすかということ」であるとし、国の発展のためには、いかに生産力を上げるかではなく「良い消費の方法」を考える必要性を説いた。

ラスキンの言う「良い(または賢い)消費」とは、何を誰が使うのかを理解し、モノが有用に消費されることを指す。前述したように、ラスキンの議論は大量消費社会以前のものであり、歴史的コンテクストの中で理解する必要がある。ただ、消費や生産の意味をそれぞれの時代において解き明かすということは、20世紀以降にアカデミア内外で台頭する消費社会・文化論においても共通の問題意識でもある。
消費は経済的なものであるだけでなく、政治的・社会的・文化的問題である
ところで、「消費社会」とは、政治や経済活動を含め生産よりも消費に主眼が置かれ、消費の社会的重要性が増大する社会を一般的に指す。さらに言えば、消費が量的にも質的にも変化することを意味する。工業化・機械化によって大量に生産されるようになった商品が、(必要以上に)大量消費される。さらに人々は、単に生きるため(サバイバルのため)だけに消費するのではなく、モノを購入し保有することによって、例えばある種の欲求を満たしたり、人と自分を差異化したりする。こうした消費に新たな価値を見出すようになった社会であるといえる。
研究者や社会批評家らの間で、消費文化や消費社会が広く論じられるようになったのは1940年代後半以降である。それ以前から、例えばソースティン・ヴェブレンのように、消費を社会的・文化的観点から論じる研究者はいたものの、米国をはじめ多くの国々で本格的な大量消費社会が到来するのは第二次世界大戦後で、それ以降、消費が経済的なものとしてだけでなく、政治的・社会的・文化的問題と密接に関わるものとして注目されるようになった。例えば経済学者のウォルト・ロストウなどは、大量に安い商品が出回るようになったことで、より多くの人が多様な商品を購入できるようになり、さらに選択の自由を享受できるようになったとして消費社会の恩恵を強調した。一方で、ジョン・ケネス・ガルブレイスやヴァンス・パッカードらは、消費を社会の弊害だと考え、企業は人為的に欲望を作り出すとともに、物質的で画一的な社会が誕生したと論じた。
映画や音楽、テレビや雑誌が、社会を画一化させ、消費者を思考停止に追い込んだ—ホルクハイマー、アドルノ
1950年代から60年代にかけて消費社会に関する議論で優勢となるのは、後者の大量消費を「社会的病理」だとみなす見方である。それに大きな影響を与えたのが、1920年代以降、ド�イツを中心にアカデミア・論壇に影響を与えてきたフランクフルト学派の論者らである。前回触れたヴァルター・ベンヤミンもこのフランクフルト学派に属する。マルクス主義の流れを汲み、資本主義システムの批判的分析を行うフランクフルト学派の中でも特に、ドイツ人哲学者・社会学者のマックス・ホルクハイマーやテオドール・アドルノは、大量消費が社会・文化に及ぼす影響に注目した。マルクスの商品や価値の論理をもとに、彼らが「文化産業(culture industry)」と呼ぶ映画や音楽産業、またテレビや雑誌などマスコミが、人々のライフスタイルや嗜好、そして社会全体を画一化させたと看破した。さらにこれらは単なる生活の画一化に留まらず、(マルクスが工場労働者に対して論じたように)消費者を思考停止に追い込み、人間性さえも奪略するものだと論じた。つまり、マルクスが労働者の疎外に注目した一方で、ホルクハイマーやアドルノは、資本主義システムの拡大、特に消費社会の拡大は、消費者の疎外に�も繋がると論じたのだ。
ホルクハイマーやアドルノ、ベンヤミンらの議論は、当時の時代背景を色濃く反映したものであった。当初、ドイツを拠点に活動していた彼らは、ナチズムが台頭する中で、いかに全体主義が社会、そして人々に影響を及ぼすのかを目の当たりにした。また、ユダヤ人であった彼らにとって、その政治的脅威は、非常に個人的なものでもあったのだ。そうした中、ベンヤミンは、「政治の美学化」をファシズムによる人員動員の中に見出した。ユダヤ人迫害を逃れて米国カリフォルニアに移ったホルクハイマーとアドルノは、新境地で拡大しつつあったハリウッドの煌びやかな商業世界や多種多様の商品が市場を席巻する状況を、全体主義社会と重ね合わせたのである。
複製技術の発達により、商品が社会生活を「植民地化」する—ドゥボール
マルクスの「物神崇拝」やフランクフルト学派、特にホルクハイマーとアドルノによる「文化産業」の議論に影響を受けた一人が、フランス人批評家のギー・ドゥボールである。1967年の著書『スペクタクルの社会』では、資本主義社会におけるマスメディアの発達で、人の生、また生活のすべてが実態を失った表象でしかなくなると論じた。ドゥボール、そしてホルクハイマーやアドルノ、ベンヤミンらは、資本主義経済における複製技術の発達により、文化(大衆文化)が商品化され、それによって社会が支配・管理されるようになると考えた。そこでは、人と人との社会関係は、スペクタクル化したイメージとしての商品どうしの関係に取って代わられ、商品が社会生活を「植民地化」するのだ。ドゥボールによれば、「スペクタクルが見えるようにする世界は存在すると同時に不在であるが、その世界は、生きられたもの〔=経験〕すべてを支配する商品の世界である。」(強調原文)こうしたドゥボールの議論は、1968年パリで勃発した五月革命に大きな影響を与えるなど、第二次世界大戦後、資本主義システムの拡大で生み出された経済的・社会的亀裂や政治体制への不満を代弁するものでもあったといえる。
幻想としての「ゆたかな社会」
フランクフルト学派の議論は、消費社会の申し子ともされる米国においても影響を与えた。コロンビア大学の社会学者だったC・ライト・ミルズによる『ホワイト・カラー』(1951年)やフランクフルト学派の流れをくむヘルベルト・マルクーゼの『一次元的人間』(1964年)などは��、経済が生産ではなく消費を中心に成り立つようになった消費資本主義社会における社会関係の変化や人々のメンタリティの変化を指摘した。そしてそうした変化は、一部のエリートによる社会・経済のコントロールや不平等の拡大などをもたらすとした。
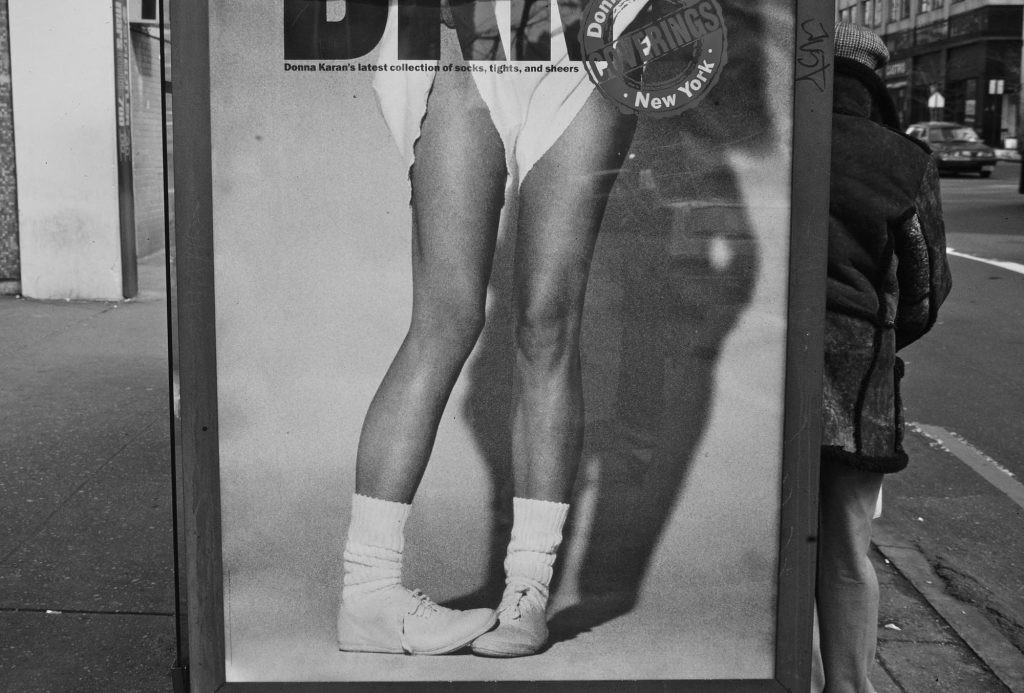
戦後の好景気に沸く米国では、中産階級層の拡大とともに、家庭電化製品、自動車、一戸建てのマイホーム等々が多くのアメリカ人家庭の手の届くところとなった。こうした「ゆたかな社会」は、メディアが作り出した言説や理想でもあり、それを享受できずにいた黒人・移民たちや低所得者層の人々も相当数存在し、大量消費社会が不平等や格差をより明確にしたともいえる。また、このゆたかさは物質的豊かさに基づいたものであり、モノに溢れる社会の中で消費者は大企業に踊らされ・騙されているとする批判も噴出した。例えば、前述のガルブライスは、『ゆたかな社会』(1958年)の中で、企業が消費者の欲望をかき立てていると非難した。また、第二波フェミニズム運動に大きな影響を与え世界的にも話題となったベティ・フリーダンの『新しい女性の創造』(1963年)は、企業広告が多くの女性(主に主婦)に理想的な家庭像を提示し、その幻想をもとにモノを買わせるよう仕向けていると断罪した。
資本主義システムがもたらした「疎外感」
1960年代末までには、大企業や拡大する資本主義経済への批判、そして消費主義を懐疑的に捉える見方は、アカデミア・論壇の外へも広がるようになっていた。1951年のある調査によると、10代のアメリカ人の半数以上が巨大企業をはじめとする経済システムを好意的に捉えているという結果だったのだが、1971年に実施した同じ調査では、その数は35パーセントにまで減少した。1969年、『フォーチュン』誌は「なぜ若者は巨大企業を非倫理的だと考えるのか」という問いを立て、資本主義システムがもたらした経済格差や不平等、そして多くの批評家らが論じた「疎外」を多くの人々が感じるようになっているからだと結論づけた。こうした大企業や資本主義体制への不信感は、いわゆる「対抗文化(カウ��ンターカルチャー)」運動や1968年の五月革命などにも現れているといえるだろう。
SNSで絶えず供給される情報が、新たなスペクタクル化をもたらす
大量生産・大量消費・技術の発達に下支えされた消費資本主義の発展が、全体主義的な管理社会へとつながるという議論は、当時の時代の産物として理解する必要がある。ただこうした議論は、現代の消費社会を考えるための一つの道標として、有用な視座を与えてもくれる。ここでは、歴史的コンテクストの違いを認識した上で、今日のソーシャルネットワークサービス(SNS)をはじめデジタル社会の拡大が、ドゥボールが見たスペクタクル化する社会といかに異なるのか(もしくは変わっていないのか)少し考えてみたい。
無限に広がるヴァーチャル世界や理論的には誰もが参加し情報発信できるSNSは、一見、管理社会をある程度乗り越えて一般の人々(大衆)が自らの意思で消費活動を行い、文化の形成に貢献しているようにも見える。だが、ドゥボールの言う「存在すると同時に不在」であるスペクタクルの世界は、まさに我々が普段接するヴァーチャル世界そのものではないだろうか。それは視覚的表象が媒介する世界であるというだけではなく、誰もが自由であるように見えて、実はその言動が管理され、監視されている。さらに、人と人の関係さえも、ある意味スペクタクル化しているのかもしれない。例えば、インスタグラムに掲載された写真に「いいね」がいくつ付けられたのかや、ツイッターのコメントがどれだけリツイートされたのかなど、ある人の表現(写真やコメント)への反響が数値化され、それが基本�的には誰でも見られるという状況、それは掲載者とオーディエンスの関係がスペクタクルとして展開されているといえるのではないだろうか。さらにそうした関係は、当人の評価やアプリ内のアルゴリズムにも影響を与えることになる。絶えず供給され、無限にループするデジタル化された情報が、新たなスペクタクルを作り上げているのかもしれない。
今回取り上げたマルクスやフランクフルト学派による議論をもとにした消費社会・文化論は、1970年代から80年代にかけてその論調に変化が見え始める。次回は、1970年代以降の消費研究に焦点を当て、消費社会について考えたい。
参考文献
『メディア・情報・消費社会』井上俊・伊藤公雄編(世界思想社 2009年)
『有閑階級の理論』ソースティン・ヴェブレン 村井章子訳(筑摩書房 2016年)[The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions (1899)]
『ゆたかな社会 決定版』ジョン・ケネス・ガルブレイス 鈴木哲太郎訳(岩波書店 2006年)[The Affluent Society (1958)]
『スペクタクルの社会』ギー・ドゥボール 木下誠訳(筑摩書房 2003年)[La société du spectacle (1967)]
『かくれた説得者』ヴァンス・パッカード 林周二訳(ダイヤモンド社 1958年)[The Hidden Persuaders (1957)]
『浪費をつくり出す人々』ヴァンス・パッカード 南博・石川弘義訳(ダイヤモンド社 1961年)[The Waste Makers (1960)]
『人間操作の時代』ヴァンス・パッカード 中村保男訳(プレジデントブックス 1978年)[The People Shapers (1972)]
『新しい女性の創造 改訂版』ベティ・フリーダン 三浦冨美子訳(大和書房 2004年)[The Feminine Mystique (1963)]
『啓蒙の弁証法』マックス・ホルクハイマー、テオドール・アドルノ 徳永恂訳(岩波書店 2007年)[Dialektik der Aufklarung: Philosophische Fragmente (1947)]
『一次元的人間―先進産業社会におけるイデオロギーの研究』ヘルベルト・マルクーゼ 生松敬三・三沢謙一訳(河出書房新社 1980年)[One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (1964)]
『ホワイト・カラー—中流階級の生活探究』C・ライト・ミルズ 杉政孝訳(東京創元社 1971年)[White Collar: The American Middle Classes (1951)]
『この最後の者にも・ごまとゆり』ジョン・ラスキン 飯塚一郎・木村正身訳(中央公論新社 2008年)[Unto This Last (1860/1862)]
『経済成長の諸段階―1つの非共産主義宣言』ウォルト・ロストウ 木村健康・久保まち子・村上泰亮訳(ダイヤモンド社 1961年)[The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (1960)]








