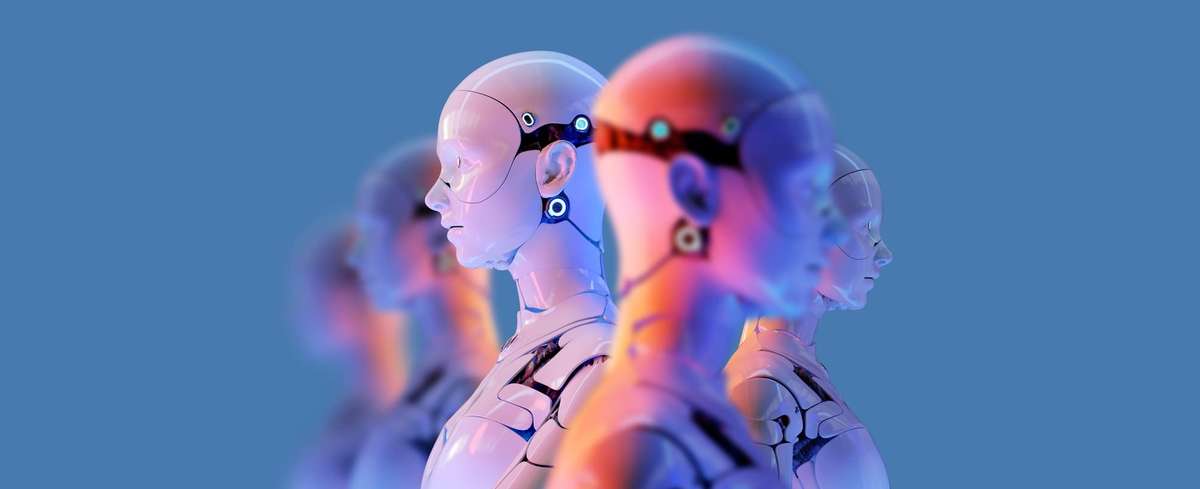1980年代のバブル真っ只中「好景気は日本の実力を反映している」と言った経済評論家もいた
1980年代の半ば、まだ現在のような経済成長の勢いがまだあまり見えない時期のインドネシア・ジャワの村落で2年ほど人類学的な調査をした。その村はジャカルタとスラバヤを結ぶ幹線道路からかなり奥まったところにあり、道路近くならもう電線は引かれていたものの、当該農村ではまだ電気がなかった。夜になると、多少裕福な家はペトロマというランタンで明かりをとっていたが、貧しい家ではバロック時代の画家の絵にでも出てきそうな灯油の火で、暗闇を照らすのも稀ではなかった。大河ドラマの夜のシーンは、たいてい明るすぎて興ざめなのは、こうした体験の後遺症である。
また当時はテレビ局が国営のTVRIしかなく、しかもそれを観るには、バッテリーをバイクに積んで、町で充電しなければならなかった。大半はインドネシア語の放送だが、週末になると、ジャワ語による影絵芝居(ワヤン)の番組とかがあり、その際は近隣の村民がこぞって家主の家に集まってきた。数年後に再訪した時には、既に村に電線が引かれ、多くの家庭がマイ・テレビを持つようになって、そうした古きよき慣習は既に消滅していた。その後衛星放送が普及し、テレビ局数も��爆発的に増え、更にウェブの時代である。近代化の力は恐ろしい。
そんな感じの生活を二年ほど続けた後に日本に帰ってくると、そこは80年代後半、バブル最盛期の日本であった。当時ジャワで普通に着ていたサファリを見て、道化研究で有名な某人類学者が連れてきた出版関係の女性に、(このバブルのご時世に)珍しい格好、と厭味を言われたのをよく覚えている。世情は浮かれまくり、息をするのも不快で家にこもりがちだったが、その後『80年代はスカだった』といった雑誌特集も出て、少なからぬ人々がそう感じていたのか、と多少溜飲を下げた記憶がある。
不思議なもので、バブルが弾けた現在では、それは明らかにただの「泡」だったと分かるのだが、その真っ最中では、必ずしも多くの人がそう理解していたとも思えなかった。実際、この好景気は日本の実力を反映していると主張していた経済評論家もいたが、バブルが弾けたあと、表舞台から消えた。だいぶ経ってから多少復活したようだったが、以前のような鼻息の荒さは感じなかった。また後に複雑系経済学についての研究会に参加した時、そこにいたマルクス経済学者たちが、「自分たちは、当時からこれはバブルだと主張していた」と言い張っていたが、『資本論』とバブル経済の関係もよく分からなかった。
「期待」は開発に作用する
私はこの分野の専門家ではないが、こうした熱狂のダイナミズムは、科学技術社会学(STS)、特にテクノロジー開発を考える上で、重要な論点の一つである。それを研究する分野は、「期待」の社会学と呼ばれており、特にテクノロジーの初期開発段階にお�いて、期待という現象が開発とどう関係するかを分析するものである。ただし、必ずしも期待という言葉だけが使われる訳ではなく、アイスランドのゲノム研究計画の歴史を分析した人類学者は、このプロジェクトに頻出する様々な「約束」について分析している。
これから勃興する(かもしれない)テクノロジーに関して、それをあたかも保証するような約束や、その未来への期待というのが、その開発に本質的に係わっているというのがこの分野の主張である。約束という話は、言語哲学者オースティン(J.Austin)の発話行為 (speech act) 論を下敷きにしているが、言語は、単に外界を描写するため(いわゆるconstative)だけでなく、それによって何かをなし遂げる(performative)という側面があるという話である。「私は約束します」と語ることは、現状を描写しているのではなく、約束すると言うことで、「約束という行為」を実行しているのである。他方、期待というのもある種言語的な特性を持つが、研究の現場と政策とを結ぶための言説的な作用という意味合いが強い。同じSTSでも、特にオランダでは研究者と政策担当者の間の距離が近く、そうしたお国柄を背景に、テクノロジー開発と期待の関係は集中的に研究されている。
テクノロジーへの熱狂にはサイクルがある
では何故、テクノロジー開発に約束や期待といった言語活動が重要なのだろうか。簡単に言えば、こうしたテクノロジーは常に生成の過程にあり、特にその初期段階では、その実物はまだ完全には存在していないからである。テクノロジー開発には長い時間と資金が要るが、実態のない何かに対して、注目を集め、資金をふくむ援助を得る必要がある。そうした社会的関心を呼び込む手段の一つがこうした期待の働きである。初期テクノロジーへの投資は、まだ見ぬ未来へのそれを意味するため、一種のギャンブルとしての性質も持つ。それが経済的にも社会的にもペイすると納得させる言葉の働きが、約束/期待なのである。
これを事後的に見れば、こうした言説と現実の開発の推移は必ずしも合致しない。期待の言語に煽られて投資をしたものの、成果が得られなかった、あるいはその逆に、ほとんど期待していなかったが大化けした、といった実例は数限りなくある。
こうした期待は言説による膨らましという面があり、現実のギャップによって、期待のレベル自体が上下するということは当然考えられる。これを単純な図式にして技術予測の手段としたのが、いわゆるハイプ(熱狂)サイクルである。先日ある全国紙の科学欄で前後の脈絡なく突然取り上げられていたが、初期テクノロジーへの関心は熱狂から始まり、失望の谷底に落ち、その後ゆっくりと現実的なレベルに落ち着くという話である。専門家たちは、実際は話がいつもこれほど単純なパターンに従う訳ではないと指摘している。開発者側が次から次へと新たなネタを繰り出して、期待があまり落ち込まないように仕向けるといったケースや、逆に大きく失速したあと、殆ど回復出来なかった例など、様々なバリエーションが報告されている。とはいえそうした乱高下の存在につ�いてはおおむね肯定している。
テクノロジー開発のスピードが追いつかなくなるとき、期待はしぼんでいく
ここで興味深いのは、研究者たちは、ハイプは現実にあわないからよろしくない、とは主張していないという点である。むしろまだ見ぬ未来への投資として、ある種必要不可欠のものと考えている。また最近では、個別のテクノロジーに関する期待から、そうした期待を支える、より広範囲な社会文化的要因といった方向に目を向ける研究者もいる。移ろいやすい期待を持続させるためには、それを支えるより大きな基盤が必要だからである。こうした社会文化的基盤を、一部の研究者はテクノロジーに関するimageryと呼んで研究しているが、この言葉はimageという単語よりも、より共同的、集合的な色彩が強い。文化社会的イメージとでも訳せようか。研究の対象になっているケースは、例えば原子力についての共通イメージであるが、それを国際比較したりするのである。最近、経済学等でも、人々が従う「物語」(ナラティブ)が経済活動に大きく影響するという議論もあるくらいだから、こうした社会文化的イメージに注目するのも一理ある。

こうした文脈からいえば、連日紙面を賑わせている生成AIの話は、まさに、今やハイプの真っ只中にあり、それへの期待を煽る言説も、特に経済誌等では熱狂のピークに達している観がある。とはいえ、既にその勢いには陰りも見え始めている。ハイプ・サイクル図式をまつまでもなく、期待の社会学において、その期待が失速するという現象は日常茶飯事であるが、そもそも初期の期待は何故失速するのであろうか。一番分かりやすい原因は、テクノロジー開発のスピードが、期待に追いつかないという点である。現場での開発者は開発の困難を熟知していて慎重だが、その周辺は、技術的細部を知らないため熱狂しやすく、また冷めやすいという研究もある。
だが、期待の失速には様々な別の、より社会的な要因もある。こうしたテクノロジー開発の弱点として、電力の歴史研究で有名なヒューズ(T. Hughes)は、「逆突出部」(reverse salient)という概念を援用しているが、これはもともと戦場において、戦線でもっとも弱い部分を示す言葉である。彼はこの言葉をテクノロジー開発に応用し、そこがネックになって全体の進展が阻害される部分のことを示している。この考えは技術面のみならず、社会文化的側面にも拡張可能で、まさにそれがもたらす社会的問題が解決できないために、結局開発が頓挫するということがありうる。フランスのある斬新な新型交通システムが、発生しうる治安の問題がネックとなって実現化しなかったという研究�もある。
生成AIの興味深い点は、社会に浸透するスピードが驚異的という点と、それに対する懸念もまたすさまじい勢いで拡大しているという点である。期待社会学が扱うテクノロジーは、しばしば開発の初期段階で、社会に対して実際にどういうインパクトを与えるかが分からないうちに失速する場合も少なくないが、こちらは今や一部で大規模な実装化が始まっているというのも珍しい。
生成AIとジャワの雨季
こうした背景にある、前述した文化社会的イメージの働きを想像してみるのも面白いが、経済誌等をみる限り、そこでのレトリックには、業務が100倍早くなる、超効率化、といった話が目立つ。昔の伝記のタイトルである「合理の熱気球」の現代版のようなイメージが中心で、バスに乗り遅れるな、という恒例の掛け声も響く。ただし前述したimageryのレベルでは、この超効率化の先に一体何があるのか、実はあまりはっきりしない。殆ど人のいない、超自動化した社会を理想としているのかは定かではない。
他方、警告を発する側のイメージは、むしろ核戦争や地球温暖化に近い、一種の終末論的な響きがある。この拡大を懸念する本邦の研究者の間からは、毒饅頭といった古典的な表現も示されたが、私ならサブプライム・ローンのようなもの、という比喩を使うかもしれない。一見おいしいもうけ話の中に、大きなリスク案件が深く埋め込まれているが、誰もそのリスクを正確に把握できなかったまま、広く買いあさられ、結局破綻したあの話である。
熱帯下のジャワには、原則乾季と雨期しかないが、後者でも朝から晩まで雨が降って�いる訳ではない。むしろ雨期に入りたての時期は、乾季でも見られなかったような、深い青色の快晴に出会うことも多い。ある時、その鮮やかさに感動しつつバイクで灼熱の県道を走っていると、少したってから、空のあちこちに白い小さな雲が殆ど等間隔で現れ始めたことがある。最初は特に気にしなかったが、少しするとそれらの雲は一様に少しずつ大きくなり、しまいには空全体があっという間に厚い雲に覆われてしまった。その後は雷鳴、そして文字通り滝のような豪雨である。今思うに、よくあの大雨の中、バイクがエンストしなかったものである。
合理の熱気球への熱狂的な期待の青空のかたわらで、ハリウッド脚本家のストや、AIに自殺を示唆されて死んだ人のニュースといった不気味な雲が、空のあちこちにぽつぽつと現れてはじめている。これが来る豪雨の先駆けなのか、それとも単なる気象のゆらぎに過ぎないのか、予断を許さない状況が続きそうである。
参考文献
『80年代の正体!―それはどんな時代だったのかハッキリ言って「スカ」だった! 』別冊宝島(JICC出版局 1990年)
『真理の工場―科学技術の社会的研究』福島真人(東京大学出版会 2017年)
『合理の熱気球―反骨の経営コンサルタント 荒木東一郎の生涯』猪飼聖紀(四海書房 1991年)
『言語と行為』J.L. オースティン 坂本百大訳(大修館書店 1978年)
『電力の歴史』T・P・ヒューズ 市場泰男訳(平凡社 1996年)
Mike Fortun(2008) Promising genomics : Iceland and deCODE Genetics in a world of speculation, University of California Press
編集部注:記事を参照された場合は、参照元として当記事をご紹介ください。