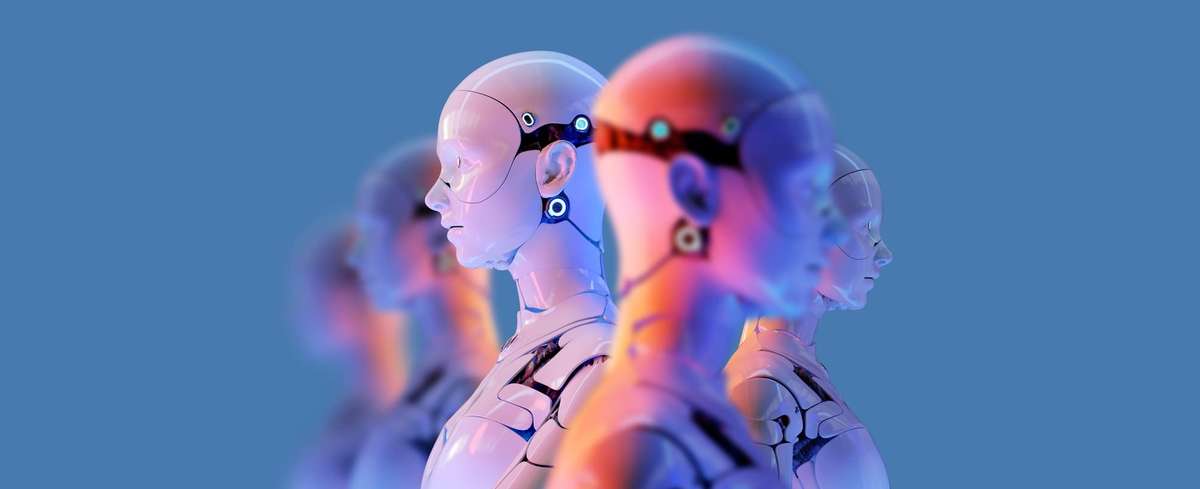動物に道徳はあるか?
人間と人間以外の存在者との道徳的関係ということで、ただちに思い浮かぶのは動物である。近年、アニマル・モラリティやアニマル・エシックスといったことばを目にする機会が増えた。そうした関心は�日本ではさほど盛り上がる気配を見せていないが、アメリカやヨーロッパではベジタリアン文化とともに一定の歴史があり、この分野の研究者も多い。G・コムストックによれば、1970年代から1999年までがトム・リーガンやピーター・シンガーらに代表される第一の波で、2000年から現在までが第二の波だとされる。第二の波では、女性研究者の数が飛躍的に伸びた。マーサ・ヌスバウムやクリスティン・アンドルーズは第二の波の代表格である(1)。この間、アメリカでのベジタリアン人口は1.2%(1978年)から6%(2018年)に増加している。
とはいえ、動物が人間とおなじ意味で道徳的だと主張するのは難しい。道徳性には一定の段階がある。よく知られているのが、道徳的行為者(moral agent)と道徳的被行為者(moral patient)との区別である。道徳的行為者とは、自らなす行為に道徳的責任を担い、行為の善し悪しを評価されるものである。同時にそれは、道徳的責任の対象でもある。これに対して、道徳的被行為者自身は責任の担い手ではないが、道徳的行為者がその利害について責任を負わなくてはならない対象である。道徳的行為者の責任の対象には、道徳的被行為者も含まれている。前者については大人の人間を、後者については子どもやペット�などを思い浮かべていただきたい。
以下では、人間と人間以外の道徳的関係をめぐる問題について、動物に焦点をあてて論じることとする。具体的には、動物を道徳的被行為者や道徳的行為者として扱ってきた日本とヨーロッパの歴史を手がかりに、人間と動物とのあいだで道徳性を問うとき何が問題になりうるか考えてみたい。
生類憐れみの令の保護対象には、捨て子や病人、高齢者が含まれていた
初代将軍徳川家康から250年余り続いた江戸幕府の歴史のなかで、第五代将軍、徳川綱吉(在位1680-1709)は、「生類憐れみの令」と名づけられた悪法で知られている(2)。この法律は、蚊のような昆虫から、猫や犬や猿までありとあらゆる生物を人間が殺傷しないように定めたものである。この法令によって保護される対象には、捨て子や病人、高齢者も含まれていた。現代の日本でも「動物愛護管理法」があり、たとえば野良猫や野鳥などを理由もなく殺傷すれば、処罰の対象となる。
綱吉の時代は元禄時代(1688-1704)とよばれ、ペットを飼育することが庶民にまで広がった時期であった。江戸時代には、海外からも多くの動物が輸入され、ペットとして愛好されていた。いっぽうで、当時は食犬の習慣があり、身分の高い人の行う鷹狩りの鷹を飼育するために犬肉が使われていたが、綱吉以降、それも禁止された。鷹狩りは権力の象徴とされ天皇や将軍がたしなんできたが、綱吉自身は鷹狩りをしなかった。
生類憐�れみ政策のもとで、犬や猫や馬をはじめとする生き物たちは、徹底して保護されるべき対象となっていた。綱吉政権はとくに、飼育している動物の毛色を記した毛付帳とよばれる台帳の提出をひとびとに命じた。現在、犬・猫・馬のものが残っている。保護される対象には、動物だけでなく、弱い人間(捨て子や病人、高齢者)もふくまれていることは注目すべきだろう。つまり、動物たちも弱い人間とおなじように弱者とみなされ、いかに人間に面倒をかけようとも、処罰の対象になることはなく、もっぱら過剰なまでの保護の対象であった。この点で、動物たちはかなり特別な道徳的被行為者であったと言える。同時に、「御犬様」といったことばからも分かるように、犬に人格や個性を付与し、具体的な個人としてあつかおうとした様子もうかがえる。個々の動物を管理するための戸籍のようなもの、毛付帳を作らせたこともそれを傍証している。
庇護されるものは所有されるもの
もちろん、こうした戸籍作成が昆虫や小動物の類いにまで及んだとは考えにくい――すでに述べたように、記録が残っているのは犬、猫、馬だけである。昆虫などは、具体的な個体ではなく漠然とした生き物の集合体として扱うしかなかったのであろう。したがって、憐れみの対象となった動物のなかには、道徳的被行為者とは言えないものも含まれていた。その憐れみは、生命にたいする態度のようなものとして受け取るべきである。
また、御犬様にせよ、迷い犬にせよ、あるいは捨て子にせよ、庇護の対象となるものは、すべて所有されるものでもあった。くわえて、所有者の責�任と管理が要求され、そこに幕府の権力が介入してきた。この点では、動物はすべて、ときの幕府の所有のものとなったと言えるかもしれない。動物は所有され庇護されるものであるいっぽうで、とくに犬は人格や個性を認められていた。人格や個性は行為の責任が生じることの必要条件であるが、所有されるものの行為の責任は通常所有者に帰せられる。所有と被所有の関係は、道徳性をめぐってひとつの論点になりうると私は考えている。次節では、この関係も念頭に置きつつ、ヨーロッパにおける動物裁判について考えてみたい。
破門されたナメクジ、罪に問われたモグラ。豚は裁判にかけられた

ヨーロッパの歴史に目をむけると、動物裁判という奇妙な出来事がある。裁判には、キリスト教がらみのもの(ecclesiastical trial)と世俗的なもの(secular trial)があった。中世末から近世にかけて、さまざまな種類の動物が「悪事を働い��た」という理由で迫害されたり処罰されたりした。毛虫やネズミ、ナメクジなどを破門にする教義法が公布され、攻撃的なペットや家畜を死刑にする教会法が制定された。昆虫や爬虫類、ネズミなどの小型哺乳類が法的に訴えられ、破門されただけでなく、大型の四足動物にも死刑を含む司法罰が科された。罪に問われたものは、毛虫、ハエ、イナゴ、ヒル、カタツムリ、ナメクジ、ミミズ、ゾウムシ、ネズミ、モグラ、キジバト、豚、牛、鶏、犬、ろば、牝馬、山羊などを中心として多岐におよんだ。アメリカの学者、E・P・エヴァンズは、37種もの生物をリストアップしている。
生類憐れみ政策によって過剰に保護される生き物が、蚊などの昆虫にまで拡大していったのと同様に、この時代のヨーロッパでは断罪される生き物のリストは広範囲に及んでいた。かたや保護される対象、かたや断罪される対象と、まるでポジとネガのように見えるこの文化的違いはきわめて興味深い。
生類憐れみ政策における象徴的な動物が犬であったのに対し、ヨーロッパで裁判にかけられた代表的な動物は豚であった。豚は家畜であるが、かつては、とくに幼い子どもにとっては危険な動物であった。この時代、ヨーロッパ各地で嬰児や子どもが豚に襲われ食い殺された事例が報告された。なぜなら、主としてイノシシから家畜化した黒豚が飼われており、現代の白豚などにくらべてずっと獰猛だったからである。白豚や赤豚が家畜化されるのは、18世紀になってからのことである。現代でも、人間の子どもを食い殺してしまうような事例がある。たとえば最近では、中国の山村での事件が報告されている(3)。アメリカでは、亡くなった飼い主の遺体を豚が食べていたという事例もある(4)。
品行方正なロバは、裁判で無罪を勝ち取った
動物の「悪事」のもうひとつの代表的な事例は、人間との性交渉である。キリスト教の立法者は、獣との性交渉を禁じるユダヤ教の掟を採用した。つまり、当時、獣と性交渉をする人間がいたことを意味するのだ。日本でも、過去の歴史において、獣姦が行われていたことは間違いない。深沢七郎の原作をもとに作られた映画『楢山節考』では、貧しい下男が欲求を満たすために雌犬を強姦するシーンが描かれている。
嬰児殺しにせよ、獣姦にせよ、その時代のヨーロッパでは、罪を犯した動物は刑罰の対象になった。動物と性交渉をした人間とともに、動物も罰せられるのである。もちろん動物たちは、善悪を区別したうえで意図をもって行為したわけではない。豚は自分のおこないを悪いと分かりつつ、子供を食い殺したわけではない。空腹のあまり、そうしたのだ。あるいは、餌と人間との区別さえつかないのかもしれない。ときには、じぶんの子どもを守ろうとしただけなのだろう。獣姦の場合は、動物は人間との性交渉を自ら望んだわけではない。
犯罪に巻き込まれたかわいそうな動物が、裁判で無罪を勝ち取ることもあった。1750年にパリ近郊のバンヴで、雌のロバがその主人とともに、獣姦で裁判にかけられた事例である。無罪となったのは、住民たちがその雌ロバの「性格」を品行方正と保証し、しかも「彼女の自由意志で」その犯罪に加担したの�ではないと認められたからである。エヴァンズの記述を見ると、ロバに人格を認めているようにもとれる。住民がロバを救おうとして裁判に提出した記録には、「ロバが有徳である」とか「慎み深い」、「だれとももめ事をおこさなかった」、「誠実であった」などと書かれていた。かりにそうだとしても、動物たちの行為は意図をもってなされたわけではない。言いかたを変えれば、意図にもとづく自由な行為ではない。別の行為もありえたのに、あえて意図的にそうしたわけではないのだ。豚は、空腹のあまり子どもを食べたのであり、殺すことを意図していたわけではない。
動物が道徳的行為者だと認めたからこそ、所有者は罪を問われなかった
最後に、裁判にかけられる動物たちの所有者はどのような立場にいたのだろうか。所有する動物との姦淫を罰せられた飼い主は、その動物とともに刑を執行された。いっぽう、子どもを殺した豚の裁判の絵には飼い主は描かれていない。所有者への責任はほぼ不問に付された。残存する裁判記録には、嬰児殺しをした豚の飼い主(所有者)に償いとして巡礼をさせた事例がほんの少しだけある。だが通常は、動物の所有者はなんの罪科にも問われず、処刑された動物の補償金をもらうことさえあった。罪を犯した動物の飼い主が罪に問われないということは、当該の動物が責任主体、道徳的行為者だと認めているのである。
とはいえ、所有者である飼い主に補償金を支払うといった事例や、飼い主が被害者にたいする贖罪金を支払わされた事例などと合わせて考えると、ここには、道徳的行為者と道徳的被行為者との単純な区別�にはうまくおさまらない動物のあり方が垣間見える。そもそも現実世界に存在しているのは、二つのあいだのさまざまな程度の中間的な存在者なのではないか。
動物を人間として取り扱う
上記で見たように、日本とヨーロッパの歴史を紐解いてみると、とりわけ犬や豚のような四つ足の動物は、ある種の人格をもった個体としてあつかわれていたことがわかる。前者では、ときに、動物が道徳的な庇護の対象(道徳的被行為者)とされ、後者では、ときに、道徳的な責任主体(道徳的行為者)とみなされた。馬鹿馬鹿しいことのようにも思えるが、いずれも、動物を人間と共通のなにかをもった存在者ととらえていたのである。動物のための戸籍を作ったことなどにも、それは表れている。
動物はときに悪意をもって犯罪に加担したと断罪された。豚が赤ん坊の耳を食いちぎった事件では、飼い主(所有者)が赤ん坊にたいする贖罪金を支払わされた。前節で言及した雌ロバについては、それが人格をもっているかのようなあつかいも受けている。さらに、ノルマンディー地方の小都市、ファレーズで14世紀に行われた雌豚の裁判の様子は、動物の人格化を如実に物語るものである。その豚は、ゆりかごのなかの嬰児の顔と腕を食いちぎり死なせてしまった。豚は裁判にかけられ、「同害刑法[報復法](lex talionis)」を適用された。処刑されるさい、身体の一部を切り落とされ服を着せられ人間のような格好をさせられた。獣であっても人間であっても犯罪者はおなじ牢屋に入れられ、おなじようにあつかわれた。
スイスの法律家、E・オーセンブリュッゲンは、動物の行為が罪になり得るためには、動物が人間化(personification)されていると考えるしかないと結論づけた。つまり、人間が動物に人格を認めているのだ。彼はその根拠として、家畜は古代や中世には家族の一員とみなされ、家臣とおなじ法的保護を受けていたと言う。フランク王国の法令集では、重荷を背負うすべての獣いわゆる牝馬は王の家臣とされ、国王の権威によって平穏に暮らすことができた。もちろん、これだけでは、動物の人間化の説明に十分な根拠をあたえるとは言えないが、野生から家畜やペットへと動物が身分を変えたことは、大きな転機であった。
もうひとつ忘れてはならないのは、14世紀以降のヨーロッパでは、動物の悪魔化があったということである。悪魔に憑依されたと見なすことによって、動物の人格化がより進みやすかったのかもしれない。動物をあたかも人格をもったもののように理解することの基礎には何があるのだろうか。なぜわれわれは、ペットや家畜を個性や人格をもった存在者とみなしてしまうのか。悪魔の憑依からは遠いところにいる現代のわれわれにとって、動物はどのような存在者であるのか。現代の動物と人間のあいだには、道徳の基礎となるようないかなる関係があるのか。次回は、所有、被所有の関係と合わせて考えてみたい。
(1) Comstock, Gary. Animal culture and morality: A new approach to industrial farm animal reform. Animal Morality Conference, 24th February 2023 in Vienna, Austria.
(2) 厳密には、「生類憐みの令」と呼ばれる法令が存在したわけではなく、「生類憐み」の趣旨を掲げたさまざまな法令の総体をその用語で呼んでいたのである(根崎 2005: 1)。
(3) Toddler mauled to death by pig after crawling into its pen(AsiaOne)
(4) Oregon farmer eaten by his pigs (The Standard)
参考文献
『犬と鷹の江戸時代 〈犬公方〉綱吉と〈鷹将軍〉吉宗』根崎光男(吉川弘文館 2016年)
「生類憐み令の成立に関する一考察―近世日本の動物保護思想との関連で―」『人間環境論集 5 (1)』 根崎光男(法政大学人間環境学会 2005年)
『生類をめぐる政治――元禄のフォークロア』塚本学(講談社 2017年)
Evans, Edward P. (1908). The criminal prosecution and capital punishment of animals. New York E. P. Button and Company.