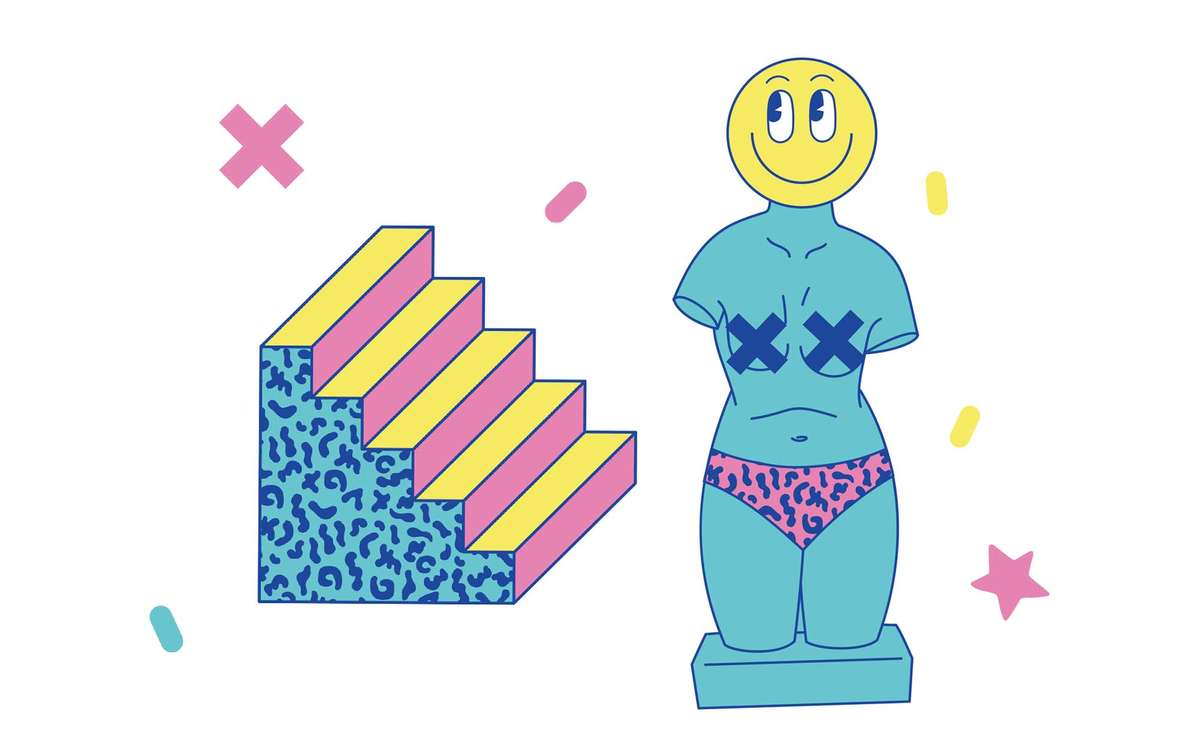視覚ばかりが論じられる一方、近代化はその他の感覚にも訪れた
あわたゞしき薄明の流れを
泳ぎつゝいそぎ飯を食むわれら
食器の音と青きむさぼりとはいともかなしく
その一枚の皿
硬き床にふれて散るとき
人�々は声をあげて警しめ合へり
宮沢賢治「公衆食堂(須田町)」『東京ノート』
この詩は、岩手から上京した宮沢賢治が、1921年(大正10年)に神田須田町にある食堂での風景を謳ったものである。詩のタイトルにもなっている「公衆食堂」とは、当時「公営食堂」や「簡易食堂」とも呼ばれ、第一次世界大戦後の物価高騰による人々の生活難の打開策として、自治体が開設した安い食事を提供する食堂のことである。この詩からは、食器が立てる音を聞きながら慌ただしく食事をする人々や皿が床に落ちて割れた時の様子、そして都会で暮らす孤独感が目に浮かぶようである。そうした情景が複数の感覚を通した経験として描かれている。例えば、「薄明の流れ」(視覚)、「飯を食む」(味覚)、「食器の音」や「声をあげて」(聴覚)。皿が「硬き床にふれて散る」という一節も触覚的な表現である。

「公衆��食堂(須田町)」が詠まれた大正時代は、近代化を目指す日本において政治・経済・文化が大きな変貌を遂げようとした激動の時代である。東京や大阪などの都市では、西洋建築物が増え始め、自動車や電車が路面を走り、洋装が流行り始めた。こうした新たな都市空間の誕生や近代化の社会的影響は、視覚性の変化として論じられることが多い。確かに視覚に訴えるメディアが発達した消費社会の台頭により、視覚の質的変化がもたらされたのは事実である。だがそれは同時に、匂いや音など他の感覚の変化も伴うものだった。つまり、宮沢賢治が描き出したように、都市の風景をはじめ周辺環境は五感を通して感じとるものなのだ。
人は「エステティックスケープ」で空間を捉える
私はこのような感覚の風景的なるものを「エステティックスケープ」という造語で呼んでいる。ここでいう「エステティック/エステティクス」とは、日本語で一般的に訳される「美的」や「美学」という意味ではなく、その語源である古代ギリシャ語「アイステーシス」が意味する感覚的・感性的認識を指す。主に1980年代以降、感覚と風景については「サウンドスケープ」や「フードスケープ」という概念が研究者たちの間で用いられてきた。エステティックスケープは、これら聴覚や味覚も含め、複数の感覚体験(または共感覚的な体験)が作り出される場として空間を捉えるもので、五感を通して理解する「風景」ともいえる。つまり芸術や美、視覚的要素のみではなく、人々の五感を通した周辺環境の認識に関わるものである。よってエステティックスケープにおける都市空間とは、都��市計画家やデザイナーらが設計・構築する物理的建築物のみならず、そこに生きる人々の風采やざわめきなど、私たちの五感を通した認識を構築する様々な要素を包含する。そしてそこには、必然的に時代性が伴うことになる。広義のファッションスタイルや音楽をはじめ、人々の生活様式がその時代特有の感覚を反映することは想像に難くない。エステティックスケープとは、こうした歴史的視点をも含む概念である。
そこへ集う人間も風景を作り出す
大正時代の東京を例にみると、当時新たに誕生した商業空間は、都市のエステティックスケープを大きく変えた。例えば、三越や白木屋など老舗百貨店は、呉服店から、洋服や化粧品、輸入食品なども販売するいわゆるデパートメントストアとして変身を遂げ、ルネッサンス様式の洋風建築の店舗を次々に建築した。それは、まだ高層ビルや洋風建築が少なかった東京で、ひときわ異彩を放つ存在だったであろう。また、当時流行した「カフェー」は、初田亨が「都市のデザインを先導」したと述べているように、店頭を装飾する色とりどりのネオンサインが夜空を焦がしていた。このカフェーは、現在の「カフェ(喫茶店)」とは異なり、コーヒーだけでなく酒も提供し、女性店員が(性的なサービスを含め)男性客の相手をする店のことである。これに対し、コーヒーや紅茶、軽食を供する喫茶店は、カフェーと区別するため「純喫茶」とあえて呼ぶこともあった。新たに作り出された都市のエステティクスは、洋風建築の外観や街灯など視覚環境のみに留まらない。当時カフェーで働いていた女性によると、カフェーは「脂粉と香料と歓声の満ちたところ。背光線の下で近代的感覚の赫灼として働くところ」だったという。店の中に一歩足を踏み入れると、そこは多種多様の感覚刺激に溢れた空間が待っていた。
さらに、そこに集う彼女、彼ら自体もエステティックスケープの一部だったといえる。吉見俊哉は、デパートや飲食店が立ち並ぶ繁華街(吉見の言葉では「盛り場」)について、単に商業的・文化的諸施設の集中した一地区としてではなく、「出来事」として捉えるべきだとして、そこに集う人びとの行動や、人びとが「盛り場との相互作用のなかで紡ぎ出していく固有の磁場(ないし社会的コード)に基づくものとして把握」するべきだと論じている。つまり、カフェーで働く白いエプロン姿の女給や、さらには街を行き交うモボやモガと呼ばれた若者たちの姿は、「モダン」な都市の象徴として、都市空間の一部を作り出し、また体現してもいたのだ。当時の盛り場における人びとの振る舞いを特徴づけるものとして吉見が指摘した、銀座でショーウィンドーを眺めがならブラブラ歩く「銀ブラ」も、銀座という一つのエ��ステティックスケープを作り出していった。そしてこのような街中の喧騒や匂い、人々が醸成する空気感の変化は、企業や官公庁で働くホワイトカラーが増加する中(「サラリーマン」という言葉が使われ始めたのもこの頃である)、中産階級層が新たなライフスタイルを模索し享受していた一つの時代を反映している。
空間が、インフォーマルに人の振る舞いを構築することもある
以上のことを踏まえると、その時代におけるエステティックスケープは、様々な経済的・政治的・社会的要因が絡み合う中で作られるということがわかる。例えばそれは、社会階級やジェンダーによって意味づけされたエステティクスを映したものでもある。大正から昭和にかけてデパートは、現代以上に「高級」なイメージを持っており、買い物客は主に中産・上流階級だった。ただそれは、低賃金の労働者たちには手の届かない商品ばかりを販売していたということだけではない。デパートという空間の雰囲気や人々が持つイメージが、階級化された場所を作り出し、デパートは一定の社会階層のみが受け入れられるところとして機能していたのだ。また、男性客もいたものの、女性が圧倒的に多かった。これは、日本のみならず欧米にも当てはまるが、近代消費主義社会において、買い物と女性性とが結び付けられジェンダー化された消費観(つまり「女性は買い物好き」だというイメージ)が生み出され、そうしたイメージが人々の行動をより強く規定するようになったことの証左でもある。
一方でカフェーは、ホワイトカラー職の男性のための空間だった。男性客と女性店員がい�るという点では、男女が共存する場所ではあった。だが、「客」と「店員」という関係性が当時の男女間の主従関係と重なることで、ジェンダー化された空間が作られていた。つまり大正時代のデパートやカフェーは、階級やジェンダーなどに基づいて、その場にいるべき者を規定し、人々がいかに振る舞うべきかを暗黙の了解のうちに構築する装置として機能していたといえる。エステティックスケープは、こうしたある意味インフォーマルな形で線引きされた都市空間の中で形成されるのである。
ヴァーチャルな「場」において、空間は人にどのような作用をもたらすか
今日、こうしたエステティックスケープは、より複雑化しているように思われる。一つには、ジェンダーや人種、国籍、さらには障害の有無など、これまで人々を区別してきたカテゴリーの多様化がある(日本ではこれらの多様化がさほど進んでいるとはいえないかもしれないが)。ユニセックスなファッションや化粧は、街を歩く人々が作り出す空間に新たなエステティクスを持ち込んだ。また、なるべく「多様」な人種やジェンダーを宣伝広告に盛り込もうとする企業の動きは、雑誌や街頭ポスターを彩る広告写真のあり方を変えた。例えばブロンドの白人女性または男性が主に起用されていたファッションモデルが、アジア系や黒人にまで広がった。ただ、こうした一見多様化したように見えるエステティックスケープも、同時に新たなカテゴリーを作り出したり、閉鎖的空間を生み出したりもする。

さらに、ソーシャルネットワークやオンラインゲームなど、ヴァーチャルな「場」が誕生したことで、エステティックスケープはリアルな空間以外にまで拡大した。ヴァーチャルであるため、その空間は無限に広がっている。さらにその場に集まる人々は、顔も名前も明らかにせずとも存在することができるようになった。そこではリアルとヴァーチャルという境界だけでなく、ファクトとフィクションの境界さえも曖昧になったといえる。こうした状況は、ジャン・ボードリヤールが1981年の著書の中で「シミュラークル」と呼んだ、消費主義社会の虚構性のもとですでに作り出され始めていたものでもある。シミュラークル化するリアルな世界だけでなく、ヴァーチャル世界が拡大する今日の社会で作り出されるエステティクスは、私たちの生活や価値観、社会との関わりをどのように変えていくのだろうか。宮沢賢治が描いたような、床に落ちて割れる皿の音を聞き、その場に居合わせた人たちが声をあげる時、そこにはエステティックな(つまり感覚・感性を通して感じ取る)人との�つながり、言い換えれば、人がそこに共存する証のようなものが生まれるのではないか。ヴァーチャルなエステティックスケープにおいて、エステティクスは社会を繋ぐものとなりうるのだろうか。
参考文献
『観察者の系譜—視覚空間の変容とモダニティ』ジョナサン・クレーリー 遠藤知巳訳(以文社 2005年)
『新装版 世界の調律—サウンドスケープとはなにか』R・マリー・シェーファー 鳥越けい子・小川博司・庄野泰子・田中直子・若尾裕訳(平凡社 2022年)
『空間の経験—身体から都市へ』イーフー・トゥアン 山本浩訳(筑摩書房 1993年)
『スペクタクルの社会』ギー・ドゥボール 木下誠訳(筑摩書房 2003年)
『モダン都市の空間博物学—東京』初田亨(彰国社 1995年)
『百貨店の誕生』初田亨(筑摩書房 1999年)
『視覚化する味覚—食を彩る資本主義』久野愛(岩波書店 2021年)
『シミュラークルとシミュレーション』ジャン・ボードリヤール 竹原あき子訳(法政大学出版局 2008年)
『胃袋の近代—食と人びとの日常史』湯澤規子(名古屋大学出版会 2018年)
『視覚都市の地政学—まなざしとしての近代』吉見俊哉(岩波書店 2016年)
『都市のドラマトゥルギー—東京・盛り場の社会史』吉見俊哉(河出書房新社 2008年)
Yasmeen, Gisèle. “‘Plastic-Bag Housewives’ and Postmodern Restaurants?: Public and Private in Bangkok’s Foodscape.” Urban Geography 17(6) (1996): 526–544.