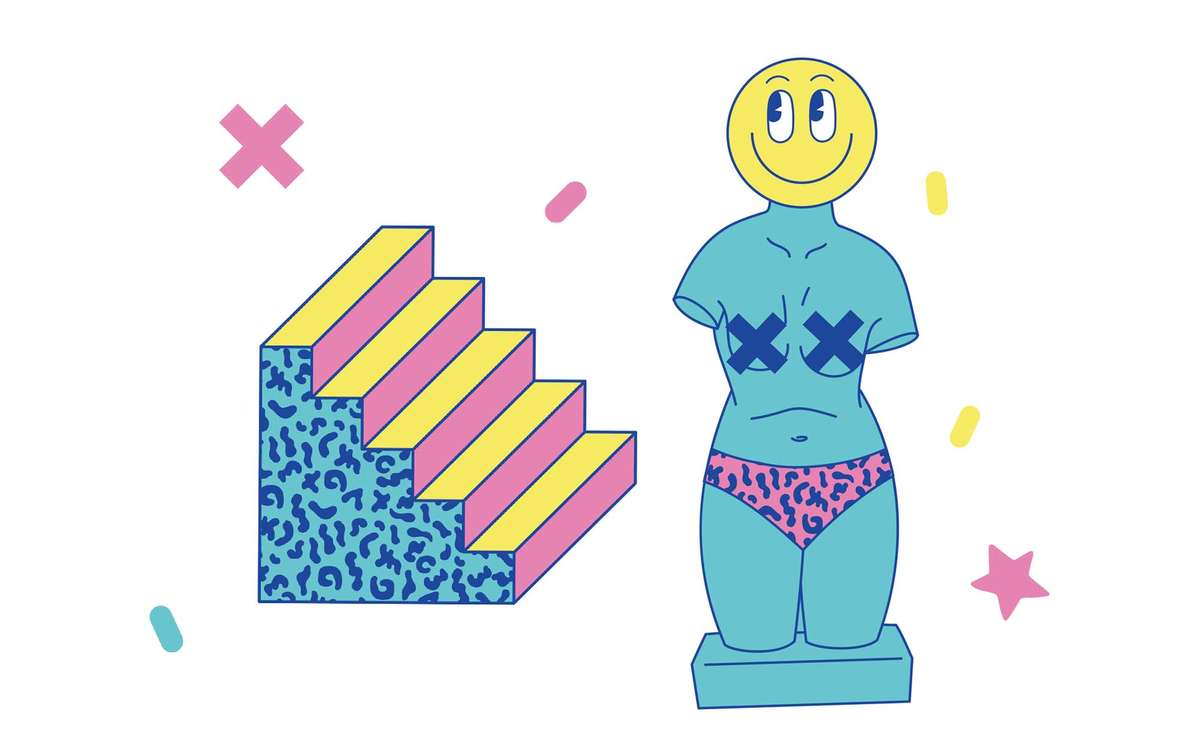デジタル時代の死別
前回、現在は親しい人との死別がより重大な意味を持っている点を指摘した。このようなとき、遺された人には耐え難い苦しみが訪れる。一部の人たちはそれになんとか対処しようと、デジタル技術をつかって苦しみを和らげることを試みている。
ある企業は、死期が近い人を取材してお別れのためのビデオを作成し、亡くなった後に遺族に渡すというプロジェクトを考えたという。死者を偲ぶ材料を作るのだそうだ。
さらに新しい技術を使ったところでは、我が子の死を受け入れられない母親がバーチャルで子どもを再現し、仮想空間でその子に出会い、最後の別れの言葉を告げていた。『クローズアップ現代プラス』で紹介されていた映像を見る限りでは、その母親はとても納得しているように見えたが、これは人によってはかえって打撃となる手法かもしれない。
さらにアメリカでは、生前に録音した歌を死後に届けるシステムが商業的になりたっているようだ。
このような死別への対処については、やはり疑問がつきまとう。これで死を受け入れることができるという人の気持ちはわかるが、人が作ったもの、構成したもの、コントロールしたものには製作者の意図が入る。それらは、おのずから生ずるもの、人と他者の交わりから生まれるものとは異なるものだ。コントロールできない物事が排除された状態で生と死を実感することは、どこか危ういことではないだろうか。