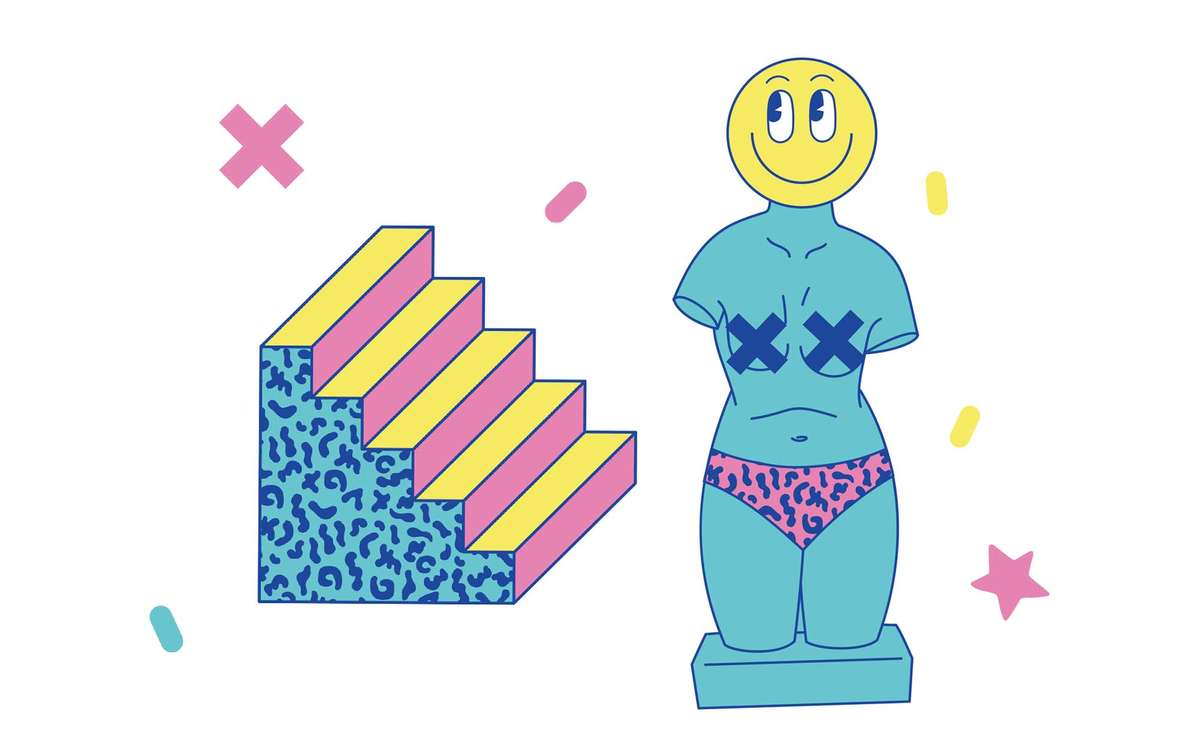会話が変わり、交わりが変わった
さらにデジタル化は、人の会話のあり方を変えてきている。携帯メールの普及以降テキストメッセージがやりとりされる機会が増えたが、声を介する会話と視覚のみに頼る会話は異なる。それもまた人間関係に影響を及ぼすだろう。同時にそれはケアのあり方、いのちの受けとめ方に関わる。
その理由の一つが時間に対する認識の違いだ。
私が7歳から10歳まで住んでいた家では、隣人が電話を持っておらずよく電話を借りに来ていた。隣人は大変お喋りな方で、私の家で平気で延々と長電話した後にさらにうちの母親と延々と喋っていた。まるでサザエさんの世界のようだが、現実にそういうことがあった。
当時もそれはもちろん少しは困るわけだが、今の困り方とは少し違う。もともとそれほど厳しく時間を管理していないから、少しぐらいの「ズレ」には寛大だった。そもそもいろいろなことが不便な時代であったから「仕方がない」と思うよりどうもしようもないことが多い。だからさまざまなことはコントロールされていない状態というのが当たり前で、会話もその一つだったのだ。井戸端会議はだからこそ発生��した。
ところが、オンラインで時間をきっちり設定して会議が行われる環境ではこのような「仕方ない」という気持ちは生まれにくい。時間管理が厳格だと雑談もしにくく、そうすると当然、他者との間で「思わぬこと」が発生する機会も少ないのだ。
いのちの厚みをつくるケアし合う関係
コロナ禍以前は食事をしながら打ち合わせをする機会というのは少なくなかったはずだが、その効用は食事によって緩められた空気のなかで温もりある関係が生じることが一つ。もう一つは、予期しないやりとりが起こることにある。そうすると、それまで思いつかなかったような面白いアイディアが出てきたり、人の知られざる側面が見えたりする。オンライン会議ではそのようなことがかなりカットされてしまう。オンライン会議では目的に沿った会話をすることが重視されるのだ。
昔はテレビでインタビューに答える力士はポツポツとしか答えなかった。しかしむしろそれが相撲取りのいいところだった。今は大分、弁舌爽やかになっている。しかし、それを聞いた後に何か心に残るかどうかは別問題だ。目的に沿った内容を話すということが、実は言葉を貧しくしている可能性がある。
ケアのためにはおしゃべりも役に立つが、沈黙の時間を交えながらともにいてケアをするというあり方がかつては多かった。それとなく相手をケアしているということが、生きていることの意味の層を厚くしていたと思う。大きな家族の主婦のケアの行為は、きょうだいや子どもたちや孫たちの暮らしぶりによって報いられていた。
一人暮らしの高齢者でも若者でもよい。他者と�の交流は限られた目的のためのやりとりが中心になり、報酬が発生するようなケアと特定の娯楽をともにする以外は、自分のことをしているというような生活が増えている。これはもちろん寂しい。相互ケアによって生じるいのちの厚みが感じにくくなってくる。これはメンタルな辛さの大きな要因ではないだろうか。ケアし合う関係を構成していくことが重要になってくる所以だ。