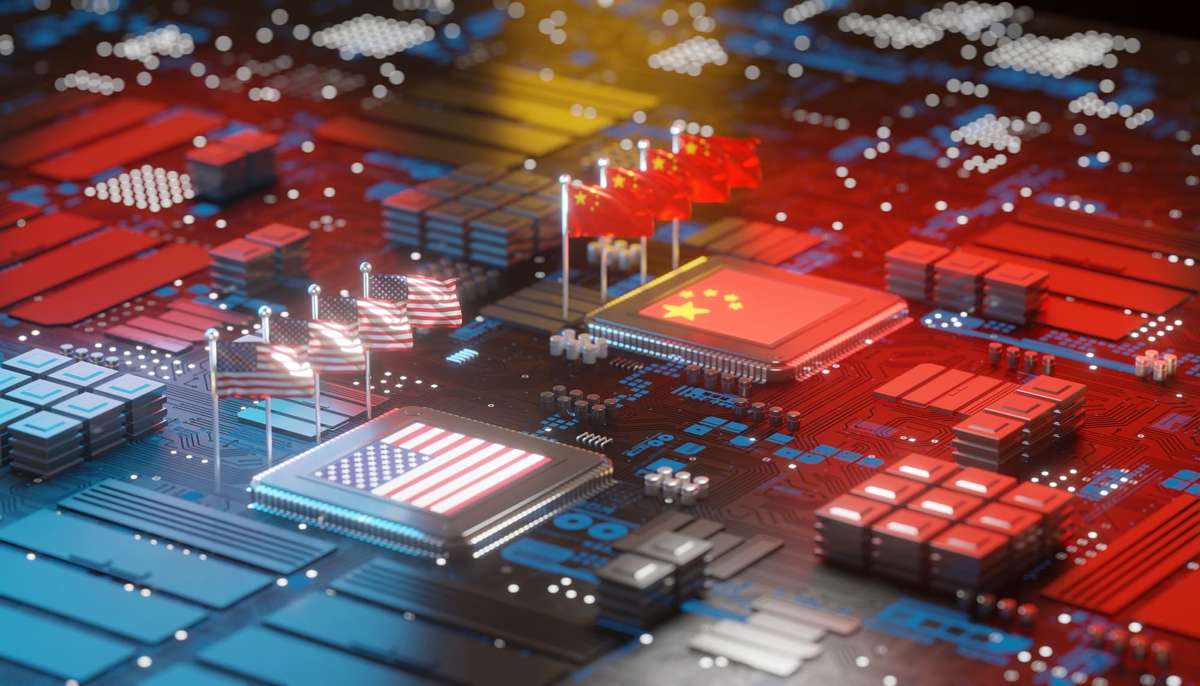コロナ禍で根底から変わってしまったコミュニケーションを再構築できるか
現在(2023年2月15日)、メキシコシティのホテルのロビーでこの文章を書いている。アメリカやメキシコは新型コロナ�ウイルスの影響からいち早く回復しつつある、というような報道もあるように見受けられるが、実際に様々な国に来てみると、やはり影響が完全になくなったわけではないことを実感する。
例えばマスクの着用率。アメリカでもメキシコでも約15パーセントの人々がマスクを着用している(2023年2月現在、村上調べ)。もちろん日本や韓国などの東アジア地域に比べれば着用率はかなり低いが、それでも15パーセントの人がまだマスクを着用していることに驚かされる。欧米、中南米はマスクに対して強い嫌悪感を持っている地域なのだ。これまで多くの欧米、中南米の国々に行ったが、マスクをしている人はほぼ皆無だった。この変化は小さくはないだろう。
世界自然遺産のオオカバマダラの生息地であるアンガンゲオの村も観光客が激減し、集落は寂れてしまっていた。
この感染症の重大な問題は、人々の健康を損ない、命を奪うことと並んで、コミュニケーションのあり方を根底から覆し、不安定な社会を生み出してしまったことだろう。一度変化を起こしてしまった人間社会の協力行動を、今後我々はどのように再構築していくことができるのだろうか?今回は、真社会性昆虫であるアリに見られる協力行動、利他的な行動に注目してみたい。
仲間のために働きに働き、自爆までする。アリたちの利他的な行動
真社会性昆虫であるアリが、単独性の生物と一線を画する特徴とは、協力行動と利他的な行動にある。
例えばツムギアリというアリがいる。このアリは東南アジアからオーストラリアに生息する樹上性のアリで、常緑の広葉樹の葉を丸くボール状にした巣を作る。働きアリたちは、葉の端を数十個体でしっかりと顎を使ってホールドし、テコの原理で曲げてボール状にする。葉と葉の隙間はなんと幼虫が吐き出す糸を使って縫い合わせるのだ。ツムギアリは、現代社会においては攻撃性の高い厄介な害虫扱いだが、古くからの農業が残っている地域では、ツムギアリの巣をそっと切り取り、自分たちの畑の周りに吊るしておくことで害虫から農作物を守っていた。これぞまさしく「生物農薬」である。

中南米に生息するEcitonやNeivamyrmexなどのグンタイアリは数十万個体の大集団で食料となる昆虫や小型の哺乳類などを襲撃し、そのまま高速で食料を持ったまま行進して、夕方になると木のウロなどにビバークポイントを作り、巨大なアリ玉となり、ゆっくりと幼虫や女王アリに給餌する。集団での見事な狩猟行動やその後の一糸乱れぬ行進、障害��物を乗り越える際に働きアリ同士が繋がってアリブリッジを作って仲間を手助けするなど高度な協力行動が見られる。中でも、かなりのスピードで移動しながらも渋滞や交通事故を起こさないその仕組みは、一体どうなっているのか、中南米でこのアリを観察しているといつも不思議に思ってしまう。
そして僕が研究しているハキリアリだ。このアリを100時間近く観察し、個体にマーキングして識別しながら行動を追ったところ、実に33種類もの労働に従事し、24時間働き詰めで、約3カ月で死んでしまうというなかなかの労働環境であることが判明した。また、他の研究では、葉を運ぶ行程で、別の個体に受け渡す行動も観察されている。一つの仕事を複数人で行うことをワークシェアリングと呼んでいるが、ハキリアリの葉を運ぶ行動の分割はさらに細分化されていて「タスクパーティショニング」と我々研究者は呼んでいる。
また、利他的行動でもアリはかなり衝撃的な地点まで到達している。東南アジアに生息するジバクアリというアリは敵が襲ってくると胸部にある分泌腺を破裂させ、黄色く粘り気のある物質を相手に吹きかける。当然、自分は死んでしまうが、コロニーを守ることができる。
自分で子どもを作るよりも、姉妹をたくさん育てたほうがよい
このように、高度な協力行動や極端な利他的行動はどのように進化してきたのだろうか?
アリやハチ��には独特な性決定のメカニズムがある。女王アリは結婚飛行をしてオスと交尾をした際に、オスの精子をお腹の中にある貯精嚢と呼ばれる袋の中に保管する。結婚飛行と交尾は女王アリの生涯でたった一回しか行われないため、保存された精子は女王アリの寿命が尽きるまで貯精嚢の中で眠り続ける。
女王アリの卵巣の管から卵が下りてくる際に、貯精嚢から精子が降りかかり受精するとメスになり、精子が降りかからないとオスになる。つまり受精卵はメス、未受精卵はオスになるのだ。これを単数倍数性(半倍数性ともいう)という。
この独特な性決定の様式がアリにもたらしたものは、血縁度の偏りだ。つまり、メス同士の血縁度は、メスとオスの間の血縁度よりも3倍高くなり、かつ親子間の血縁度よりも平均で25%も多く遺伝要素を共有することになるのだ。このことにより、メスの中にはわざわざ自分で子どもを作るよりも姉妹をたくさん育てたほうが、より多くの自分に近い遺伝子を次世代に残せることができるようになる。これがアリやハチにおける不妊のワーカーの進化要因であると考えられている。
しかしながら、血縁度の偏りだけで真社会性の進化を説明することは難しい。
同じような性決定のメカニズムを持っていても、真社会性があまり進化しなかった昆虫もいる
例えば、全く同じ性決定のメカニズムを持っているアザミウマという昆虫がいる。この昆虫は体サイズが小さく、硬いゴールと呼ばれる虫こぶに閉じこもり、集団を作るため、園芸や農業に大きな被害をもたらす。アザミウマは血縁度の偏りが存在しているにも関わらず、記載されている約5,000種のうち真社会性のものはたったの7種(わずか0.1%)に過ぎない。なぜアザミウマでは真社会性が進化しにくいのだろうか?その要因には次のようなものが考えられている。
(1)寿命が短い。基本的にアザミウマは単年性である。
(2)体サイズが小さい。アリよりもさらに小さいため、コミュニケーションを取るための器官を持つのが困難である。
ではどういった条件で、協力行動や利他的行動が高度に洗練されたのだろうか?
一つには、食料でもあり家でもある植物の特徴による。あまり栄養価が高くなく、ゆっくりとしか成長しない植物しか生えていない地域では、アザミウマはゆっくりとしか成長できず寿命が長くなる。また、虫こぶがきちんとできないため、捕食圧が高くなる傾向にある。このような厳しい環境下においてアザミウマの戦略が「隠れて逃げる」戦略から「留まって戦う」戦略へとシフトしたものと考えられている。しかしながら、体の小ささはいかんともし難く、アザミウマにおいては分散傾向が強かったり、コミュニケーションが進化しなかったりしたため、遺伝的な背景等しては真社会性が進化してもおかしくないのに、わずか7種でしか確認されていないのだ。
真社会性が進化した後に特殊な遺伝子が活性化。さらに複雑な社会を形成したハダカデバネズミ

厳しい環境と社会性に関しては、数少ない真社会性哺乳類でも同様のことが観察されている。中東の砂漠地域に生息するハダカデバネズミは、真社会性哺乳類として有名であり、かつその見た目や行動のユニークさから一部の人々に愛されている(もちろん僕も大好きだ)。ハダカデバネズミは砂漠の地下にトンネルを掘り、その中で、300個体ほどで集団生活をしている。2019年にノーベル医学生理学賞を受賞したテーマが「HIF (低酸素誘導因子-プロリン水酸化酵素(hypoxia inducible factor-prolyl hydroxylase)」(ヒフと発音する)という遺伝子の機能解明であったが、実はハダカデバネズミはこのHIF遺伝子が活発に発現し、寿命を伸ばしたり、ガン化を防いだりしているということが近年の研究から明らかになっている。HIF遺伝子は低酸素状態で機能することが分かっており、トンネル内で多数のハダカデバネズミが生息する環境が低酸素状態を生み出し、それに適応した結果、HIFが活発に発現し、長寿命かつガン化などからも解放され、真社会性が進化しやすくなったと推測されている。
ハダカデバネズミでは、実際にはシロアリなどと同じく「親による子の操作」が真社会性進化の主要因だとされている。シロアリは女王や王が腸内共生微生物を子に受け渡すタイミングや��量を調整することで、カースト分化を制御して不妊のワーカーを生み出しているとされている。ハダカデバネズミは女王ネズミのおしっこの中に、繁殖を抑制する匂い物質が含まれていて、子どもたちを不妊化してしまう。
恐らくハダカデバネズミでは、真社会性が進化した後に、HIFなどの特殊な環境で発現が活性化される遺伝子が活性化され、より社会構造が複雑化できたという方が実態に即しているかもしれない。
協力行動や利他的な行動が増える条件
ここまで見てきたように、真社会性を担保する協力行動や利他的な行動に必要な条件をまとめると、
・遺伝的なユニークさがあり、血縁度が高くなる
・厳しい環境のせいで寿命が伸び、捕食圧なども大きくなる
・密なコミュニケーションが取れる
となるだろう。
上記のなかで、人間が意図的に選び取れるものは3つめのコミュニケーションしかない。遺伝的なユニークさはすぐに獲得できるものではないし、人類の多くは捕食の脅威からは逃れることができている。
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は、我々に多くの対策を求めてきた。DXもその一つになるだろう。社会性進化の一つの大きな要因である病原微生物の存在は、DXも含めた人間社会の構造変化にも非常に大きな影響を残すものなのだと、今更ながらに実感している。特に、リモートでのコミュニケーションが多くなった結果、共有できる情報量が減少し、それが要因で社会不安や協力行動の欠如がこれから増えていくのではないかと思われてならない。生物は視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の五感をフルに使ってコミュニケーシ��ョンを取ることで様々な情報を伝達し、利益を共有することで社会性が進化してきたといえる。
DXも一つのオプションとして、より多様なコミュニケーションを復活させられるよう、そろそろ勇気を出して僕らも少しずつ旅に出てみるのも良いのかもしれない。