人は自分の習慣や規範的思考を変えるのに、明示的なトリガーを必要とする
画期的なものや人、出来事に出会ったとき、人はそれを境にそれまでの考え方やふるまいを変えることがある。よく著名人のインタビューなどで「あなたを変えたひと言は何ですか」のような質問を耳にするが、誰かが何の気なしに言ったアドバイスや、モットーのようなものが自分の中に強く残り、その後の行動を変容させることがままあるのだ。もちろん、機が熟していた、たまたま変わる時期に来ていた、と考えることもできるが、そうした積み重なりにおいてあるひと言がきっかけとなって作用したことに変わりはない。教育の��現場で日々投げかける言葉のうち、どれが学生の大きな成長のトリガーとなるかは誰にも読めない。どれもが学生のマインドセットを変える起点となるポテンシャルを持っている。ささいなひとことが刺激となり大化けして、誰かにとっての「創造的翻訳」、つまりポジティブな変化を起こすかもしれないのだ。
おもしろいのは、人が自分の習慣や規範的思考を変えるのに、何かしら明示的なトリガーを必要とする傾向である。このシリーズで紹介してきた翻訳学的には、きっかけとなる情報コンテンツを「起点テキスト(いわゆる原文)」、それによって生み出された思考や行動を「目標テキスト(訳文)」と見立てることができる。その間の変化を実現する行為がトランスレーションであり、両者の差がシフト(変容)である。
古くから行われてきた創造的な翻訳
さて、今回は起点テキストと目標テキストが等価性(同じ意味)を持つことにとらわれずに自由な表現を産み出す創造的(クリエイティブ)翻訳の話をしたい。前回サイエンスコミュニケーションの話題に触れたが、ある科学的事象を、子供にも納得できるように易しく表現し、伝える必要があるとしよう。アインシュタインが、6歳の子供にもわかるように説明できなければ理解したとは言えない、と言ったが、科学的法則そのものは多くの場合、シンプルかつ明確である。

とは言え、たとえば分子や原子のように、肉眼で見えないものを子供は知るはずがないし、概念的なものも伝えにくい。では、どうやって表現するか。子供の目線に立ち、知っていること、周りにあるものを活用し、具体例をもってくる、似ているものにたとえる、事象を目の当たりに見せるなど、科学とその子供が生きている世界をつなぐしかけが必要だろう。
少々古いが、福澤諭吉による科学書の日本語訳『訓蒙窮理図解』(1866)から例を紹介しよう。
起点テキスト(英語):Heat being applied beneath, the lower particles become expanded and rarefied. They therefore ascend, carrying up their heat, while cooler and heavier particles from above take their place … The process of convection is exhibited when water is set over a fire to boil. The particles soon begin to move, as may be shown by throwing in some powdered amber, which is seen to rise and descend…(Quackenbos 1866, 202-203 no.501)
目標テキスト(訳文):さて,熱に由りて容(かさ)を増ませば,軽(かろ)くなるべきの理りなり.故に風ふ呂を沸わかすとき,下より火を焚きて,湯は上の方より先に暖まる理合も,これにて合点すべし.風呂の底にて熱を受くれば,其の水脹れて軽くなるゆへ上に浮かび,上より冷たき水の交代して,始終上下に入り替るなり硝子(びいどろ)の急須にて湯を沸かせば,其の昇降(のぼりくだり) の様子を明かに見るべし�.(福澤 1868, 第一巻 第一章「温気の事」12)
ここでは加熱に伴う水の対流について説明されている。英文では明確に言語化はされていないが、ガラス容器での現象を前提に解説しているのに対し、日本語訳では同じ現象を「風呂」を用いて解説している。当時の風呂は洋風のものではなく日本文化固有の形状を持つアイテムだったので、ガラス容器から「日本式風呂桶」への文化的転置が起こった、と解釈できる。また、英文の”particle”(粒子)は科学を理解する上で重要な概念だが、福澤はこの書全体を通じてこれを徹底的に暗示化している。加熱による粒子の膨張と,それにより軽くなるという原理は、日本語版では、実際に体感できる現象(風呂の上部と下部の温度の違い)に変換して説明されている。起点テキストと比べると、科学的には踏み込まず、一段浅いレベルとなっている。
(アミール・野原(2014)「異文化コミュニケーターとしての福澤諭吉 : 異文化コミュニケーションの視点から見た科学コミュニケーション」『科学技術コミュニケーション』16, 59-74)
子供に限らず大人にとっても、ふだん接していない事がらを理解する、あるいは通り慣れていない道筋を通ってものごとを理解するのは骨が折れるので、上手く伝えるコミュニケーションの工夫は昔から縷々試されているのである。
工夫して伝えようとすればするほど、何か別のものになっていく?
科学を専門家と非専門家が共有するためのサイエンスコミュニケーションの理論と実践は上記のような前提�で発展していくのだが、工夫して伝えようとすればするほど、それはもはや科学ではない、と思う瞬間がときどき訪れる。わかりにくいからわかりやすくしようとする、言い換える、足す、減らす。わかってもらえた瞬間にそのコンテンツを良く視ると、それは科学を元ネタとした、何か違うものにも見えるのである。以前の記事で、過冷却をテーマにしアイリッシュバーで実施したサイエンスカフェについて紹介したが、その一環で、学生が水の分子を「演じ」、その動きを身体で表現する場面があった。
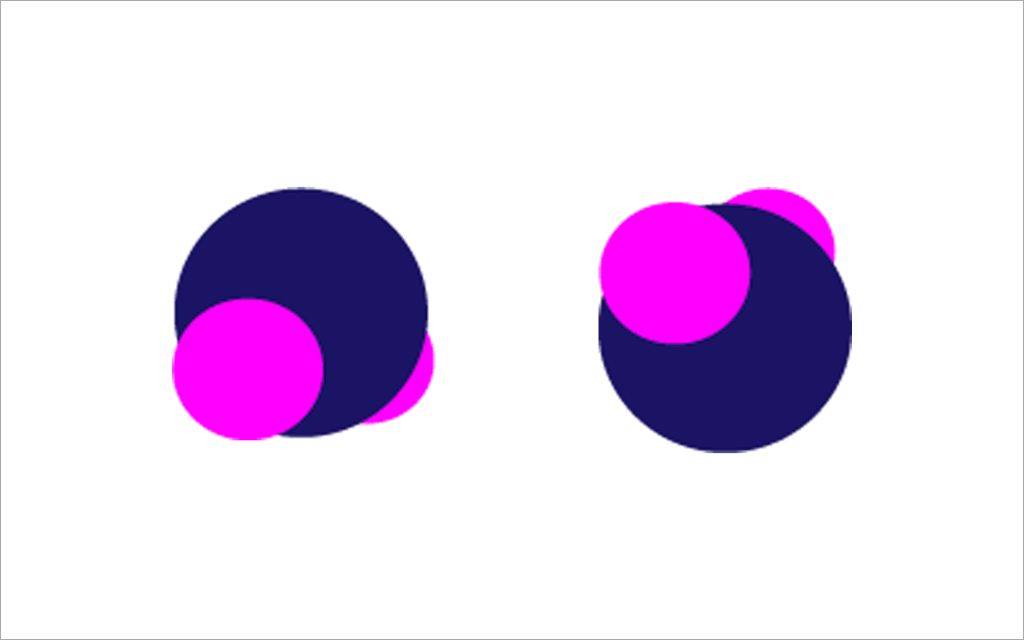
液状化して水になるとき、熱が加わりお湯になるとき。温度が下がり、氷になるとき。そして、刺激によって凍る瞬間。それぞれのシーンで、分子はどう動いているのか。その動きを真面目な顔で体現した学生らのパフォーマンスは秀逸�だった、と思う。用いたコミュニケーション技法(レトリック)は比喩であり、擬人化であり、単純化でもあった。何より、会場の笑いを誘うユーモアがそこにあったが、「元ネタ」である過冷却現象には、笑いの要素はどこにもない。とすると、過冷却コンテンツからこのパフォーマンス、そしてそれをさらに編集したビデオコンテンツへの翻訳プロセス上、起こったことは何なのだろう。科学を易しく伝えた、だけでは言い表せない何かがそのコミュニケーション上にある。
パニーニをサンドイッチと訳すことの功罪
たとえば増幅というストラテジーを使うことがある。たとえば”I can’t believe it!”というセリフは「信じられない!」と訳すことができようが、「まさか、信じられない」と訳される場合もある。この場合の「まさか」はどこから来るのか。日本語ではこの手の副詞や感動詞は種類が多く、会話で多用することが知られている。英語の原文にはそれに直接当たる語は見当たらないが、「日本語の会話だったら言うはず、あるいは言うと自然」だから補われているプラグマティックなケースである。したがって、受けるインパクトはほぼ同じと考えることもできるし、「まさか」を入れることで翻訳プロセス上、何らかの要素たとえば「心底驚いたという心象」が増幅されている、と考えることもできるだろう。
同様に、原文になかったものを減らしたり(削減)、消したり(省略)、先の福澤の翻訳にあった通り、見当たらないアイテムが登場した時には、日本で知られているそれらしいものに置き換えてみたり(文化的転置)、いろいろな工夫が戦略的に行�われてるのが翻訳である。最後の転置の例としては、原文に”Panini”(イタリアの温かいサンドイッチ)が出てきたときに、誰もが知っていて指す種類もより守備範囲の広い「サンドイッチ」に置き換える、というようなケースもある。それで話は十分通る、と思う反面、どんなサンドイッチだったのか詳細が伝わらない、イタリアらしさが失われる、また「パニーニ」を知らない人がそれに初めて出会う機会が失われる……など、文化的レファレンスの調整にプラス面とマイナス面は常に同居しているのである。
サイエンスコミュニケーションは科学的知識だけを正確に伝えるものではないのでは?
さて、サイエンスコミュニケーションに話を戻そう。理系でなくとも、小学校の頃までは理科が好きだった、という人も多いのではないか。そういう人に尋ねると、手を動かす実験や野外観察が楽しかった、化学反応を顕微鏡で見て面白かった……のように、目に見える現象を、理屈を超えて体感することを楽しんだ人が多いように思う。大人になるとなかなかそうした機会はないけれど、科学技術情報には、とらえられる現象、証明された事実を超えて、奇妙な「面白さ」の種が潜んでいる。それは、人が「面白い」をはじめとして、いろいろなことを感じ考えることができる面をいくつも持っているということである。科学は、それ自体で終わる必要がないのだ。人の思考や感情を動かすということは、それをトリガーとして、次の何かが創れるということでもある。翻訳にたとえるなら、科学技術を起点テキストとして見るとき、いろいろな翻訳が可能な素材だとも言えるのではないか。
子供がサイエンスコミュニケーション、たとえば英国の伝統あるクリスマス・レクチャー(Royal Institution)や科学博物館の展示を楽しむとき、登場するロボットや昆虫やエンジンや遺伝子……それらがどう表現されているか、演出はさまざまであり、コミュニケーションチームの力の見せどころでもある。クリスマス・レクチャーで言われているのが1時間の催しの中で、数分に一回(4分説と6分説を耳にした)笑わせることが伝統的に決まっているのだという。彼らの認識の中で、コミュニケーションは情報出しではなく、しかけを通して相手が受け取る体感、そのあとで見せるリアクション(笑う、触ろうとする、もっと知ろうとする)も含んでいる。これは科学を起点に据えた、人のトランスレーションの実現である。彼らが受け取り発現するものの形式は形式知としての科学を超えている。それに名前を付けることは難しいのだが、最初は科学的情報伝達を目的として出発したコミュニケーションだが、科学を忠実に伝えるミッションをはるかに超えて機能する、別の媒体に変容した何かである。そんな多彩な翻訳を可能にする科学というコンテンツは、創造的活動のソース(起点)として、もっとオープンに共有されてよい、と思う。








