「科学技術によるイノベーション」に対する真っ向からの提言
新しい資本主義の一つ目の柱である「科学技術によるイノベーション」に対し、真っ向からの提言となる論考がある。
科学研究によってイノベーションを起こすためには、まだ成果が見えにくい土壌に広く水を蒔き、芽吹きを補助する必要があるだろう。しかしこの段階で「自称・目利き」がどこか集中的に資金を投入しても意味がない。資金投下の時期をきちんと見極めるべきだ。

外から見えるのはいわば研究の大動脈だけだから、そこに血流を集中させれば能率があがるだろうというので、選択と集中という話になり、やれ卓越化だ、やれハーバード大学を見習えという話になる。だが、STS研究者のカロン(M.Callon)が指摘したように、研究の発展段階を初期と後期に分けると、研究分野の初期は、少数の研究者が未知の領域についてバラバラに探索する過程である。この段階では、研究者同士がお互いの試行錯誤を通じてネットワークを形成する。そして、ここで大金を投入しても意味がないとカロンは指摘する。他方、ゲノム研究のように装置の大型化と高速度化が勝負のわかれ目といった段階になれば、投入資金の額がかなり効いてくるのである。
『研究の毛細血管を干上がらせる「選択と集中」への熱狂』福島真人 (東京大学大学院・情報学環教授)
「農」の現場を効率化させるだけではもったいない
「デジタル田園都市国家構想による地方活性化」のなかには、「農業におけるデジタル技術の実装等を通じたスマート化を生産現場で推進しています。これにより、農業を若者にとって魅力のある産業とし、農業の成長産業化を図ります。」という記述がある。
農業の安定化・効率化を考えているのだろうが、実は農業には作物を育てること以外にもたくさんの効能がある。
ケア事業を担う民間団体への支援も視野に入れてほしい。

実は農を用いたケアは諸外国ではケアファームと呼ばれ、特にオランダで盛んにおこなわれている。発達障碍、長期失業、薬物依存、精神疾患、そして高齢や認知症といった様々な課題を抱える人がリカバ��リーを目指して農園で活動しており、ケアファームで生計を立てている事業者が1,000以上あるとされる。
わが国では近年発達障碍をもつ人が、企業の運営する農業事業所で働くという契機で盛んになっている。これは企業側にも障碍をもつ人の雇用率が向上するというメリットがある。もちろん光があれば影もあるが、ここでは触れないでおく。しかし高齢者のケアへの応用はまだ始まったばかりである。
考えてみれば、農作業はわれわれ現生人類にとって最も馴染みのある基本動作であったのではないか?農作業には、自然を楽しむ、仲間と交流する、適度な運動をする、命を慈しむ、収穫を楽しむといった喜びがある。大きな可能性があるのではないだろうか?
『10人に1人が認知症をもつ時代、人類の基本動作である「農作業」が危険な2分法を回避する』岡村毅(東京都健康長寿医療センター研究所研究副部長)
地方の課題はソフト面にもある
「新しい資本主義」の主役は地方であり、「地域が抱える人口減少、高齢化、産業空洞化などの課題をデジタルの力を活用することによって解決し、地方から国全体へボトムアップの成長を実現していきます。」とのことである。
そのために地方は、ハード面だけでなく、ソフトの面の課題にも目を向けなくてはならない。特に若い世代に来てほしいと願うのならば、地方コミュニティのあり方をよく考える必要がある。

コミュニティには大きく分けて2つの型がある。「農村型コミュニティ」と「都市型コミュニティ」である。
日本で作られるコミュニティは、一般的には農村型コミュニティと呼べるものであることが多い。農村型コミュニティとは、同質的な人々が集団となり、情緒的な一体感をもって結びついている社会だ。ここでの人々は、空気を読み合い、互いを忖度し、同調性を重んじる。
一方で、都市型コミュニティはより緩やかなつながりで集団が形成されている。個人が独立した存在であり、人間関係は比較的ドライで、異質な個人も含まれる。集団を超えたつながりも発生し、空気を読むことよりも、言語で論理的に説明することを好む。
旧来の日本社会は農村型コミュニティが多数だった。そのために、コミュニティとは息苦しくて抑圧性が高いものだと理解されがちだったのだ。だが、都市型のコミュニティならどうだろう。これなら、コミュニティに属することへの抵抗感が随分と薄まるのではないか。だからこれからの日本においてコミュニティを考えるときは、いかに都市型コミュニティを増やしていけるかが重要になる。『新しいコミュニティを実現するため��に』広井良典(京都大学・人と社会の未来研究院教授)
DXの肝はデータを使えるようにすること
当然「デジタル田園都市国家構想による地方活性化」のなかには、DXの推進も含まれている。DXにおいて重要なことは、何もかもをゼロベースで作っていくことではない。既存のデータ等を上手く利用できるように基盤を整えることが大切だ。

DXとは、単に事象をデジタル化して業務効率を向上させることを指すのではない。もちろん、アナログだった事象をデジタル化してデータとして取り扱えるようにすることで、結果として新しい気付きがあり、ビジネスの変革が実現できれば、それは立派なDXになる。しかし、デジタルデータになったことで一部の業務効率を上げて満足してしまっては、DXには到達しない。
DXで重要なのは、データとデジタル技術の活用をする上で、最大限活用できるインフラを整えることだ。どんなデータにも、必ず価値がある。社内のデータでも、現在はバラバラなシステムで利用されている複数のデータを横串で分析することで、新しい価値が見えてくる可能性は高い。『日本でDXが成功しない本当の理由』髙橋信久(Neutrix Cloud Japan CTO)

AIのプロジェクトがほとんど失敗するのは、AIが使えないということではなく、集めたデータを加工するコストが見合わないからです。今のやり方では動かすことはできても、加工コストがかさんで儲からないのですね。AIが見せるバラ色の未来と現実とのギャップは、誰かが埋めてあげないといけないと感じています。
(データのコストを下げるためには)効率を上げるということです。そのためにはデータを集約する必要があります。同じようなデータがたくさんあれば、加工の効率が上がります。自動化ツールを使ったとしても、データの量が多いほど効率が上がり、コストが下がります。「大量のデータを処理した方が良い」ということを、皆が理解する必要があります。『「2025年の崖」に落ちないためのDXソリューションを考えよ』佐々木隆仁(リーガルテック株式会社代表取締役社長)
あるものを使う、できる人にやってもらう
労働人口が減りゆく場所に��おいては、何もかもをプロ頼み前提にすることには無理が生じる。可能なジャンルは、素人が楽しんで課題解決に挑むことをサポートしてはどうか。

コミュニティ大工による空き家再生の価値を、有木さんは次のように言い表している。「自分にできることから家づくりに関わることができる嬉しさを分かち合え、ともに汗を流し、同じ釜の飯を食べ、言葉を交わすというかけがえのない時間を生み出し、たくさんの人が応援したくなるような地域への思いを工事で表現でき、空き家再生を通じて地域がハード・ソフト両面でパワーアップできる」と。
そして、コミュニティ大工の楽しさについて聞くと、自分が成長する楽しさ、交流し世界が広がる楽しさ、誰かの力になる楽しさ、そしてこれからの夢が広がる楽しさがあると力強く答えてくれた。『素人チームが街を強くする。コミュニティ大工が築く地域の未来』松村秀一(東京大学大学院・工学系研究科特任教授)
「脱炭素」は稼ぐために
「カーボンニュートラルの実現」の項目でははっきりとは書かれていないが、脱炭素政策の根底にあるべきは「カーボンニュートラルに乗じて稼ぐこと」である。

未だ、日本の企業は「脱炭素に対応する」という言葉を使うことが多いが、はっきり言ってそれだけではパワーは失われる。重要なのは、脱炭素の計画をすることである。律儀に一つずつ対応をして結果をだしても、株価はめったに上がらない。脱炭素に関心のある投資家の期待に働きかけるためには、ビジョンを示す必要がある。
脱炭素は今や金を稼ぐ手段となりつつある。そして、金を稼ぐというのはすなわち権力闘争である。金額は、その数だけ人や物事を動かす力を持っていることを意味する。この権力闘争に負ければ、日本にできることは単純に減ってしまう。『脱炭素が禍いの種になるとき』大場紀章(ポスト石油戦略研究所代表)
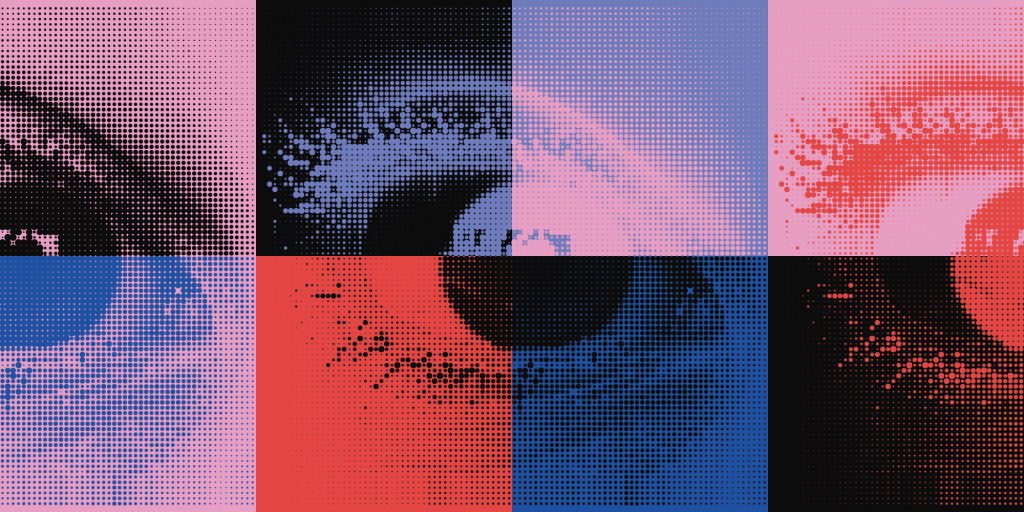
テスラって、ほとんど自分のお金を使わずに工場を作っちゃうんです。例えばベルリンの工場とか上海の工場とかありますけど、あれもほとんど政府側の誘致です。今後の経済は、労働力の安いところでモノを作るというところから、カーボンの排出量の低いところでモノを作る方へと転換するんですね。資本主義のルールが変わるという宣言をみんながしているんです。日本はまだあまりそれに気づいていないので、労働力を下げて“ものづくり”的な話をしているんですけど、これからはカーボンの排出を下げないと、ものづくりができなくなるんです。ヨーロッパは、資本主義経済をよく研究して、ヨーロッパ流に書き換えているんです。『環境問題を解決したければ、我慢をさせない方がいい』川端由美 (環境・モータージャーナリスト)
万博を自己満足で終わらせない
やや細かい項目であるが、「科学技術・イノベーション」の枠では、2025年の大阪・関西万博にも触れられている。
「科学技術や、イノベーション��の力で、未来を切り拓いていく日本の姿を世界に発信していきます。世界中の人々に「夢」と「驚き」を与えるような国際博覧会とするべく、必要な経費を確保し、円滑に準備を進めます。」とあるが、ただの発表の場として終わらせず、この先の課題解決につながる展示になることを期待したい。

万国博覧会は、それ自体が巨大なデザインイベントとしての側面を有している。多くのパビリオンが林立する会場で、参加各国や企業はいかにして自国や自社の魅力や技術を訴求するのか。博覧会国際事務局(BIE)の方針転換によって万博が課題解決型イベントへと変容を遂げた21世紀には、ここにいかにして与えられた課題へのソリューションを提示するのかという要素が加わった。上記のプロセスに従って最適解を導く「万博思考」の登場は必然的な事態だったと言ってもよい。『アスタナ万博で放たれたタイの異彩。「万博思考」はこうして生まれる』暮沢剛巳(東京工科大学デザイン学部教授)
取るべきところから取らずに分配するだと?
「新しい資本主義」では「成長と分配の好循環」が大切なのだそうだ(その中に、これまでに上げてきた成長戦略の他、分配戦略や全ての人が生きがいを感じられる社会の実現が含まれている)。そのためには、当然分配のための財源を正しく徴収しなければならない。巨大企業や資本家が税逃れを続けている状況で、それが本当に可能なのかを真剣に考えるべきだ。

ここ数十年間で、金融部門は世界経済のなかでの役割をますます増加させた。金融部門が、�巨額の利益が出る部門であることは確かである。問題は、非常に利益大きな利益を生じる金融分野が、現実には付加価値を直接には増加させていない点にある。FIRE部門と呼ばれるFinance=金融、insurance=保険、re=real estate=不動産は、中間投入ないし税としてカウントすべきであり、GDPに入れるべきではない。これは、本書の理論的ベースのひとつをなしたヤコブ・アッサの考えでもある(ヤコブ・アッサ・玉木俊明訳『過剰な金融社会』知泉書館、2020年)。
(中略)
巨額の利益をもたらす金融部門では、非常に優秀な人々働いている。われわれは、人々の生活水準を向上させることのない部門で優秀な人々が働き、巨額の富を獲得し、しかし社会は全体として豊かにはならないというジレンマに直面している。富の増加が豊かな社会をもたらすわけではないということである。『ピケティが見逃した「金融社会」』玉木俊明(京都産業大学・経済学部教授)








