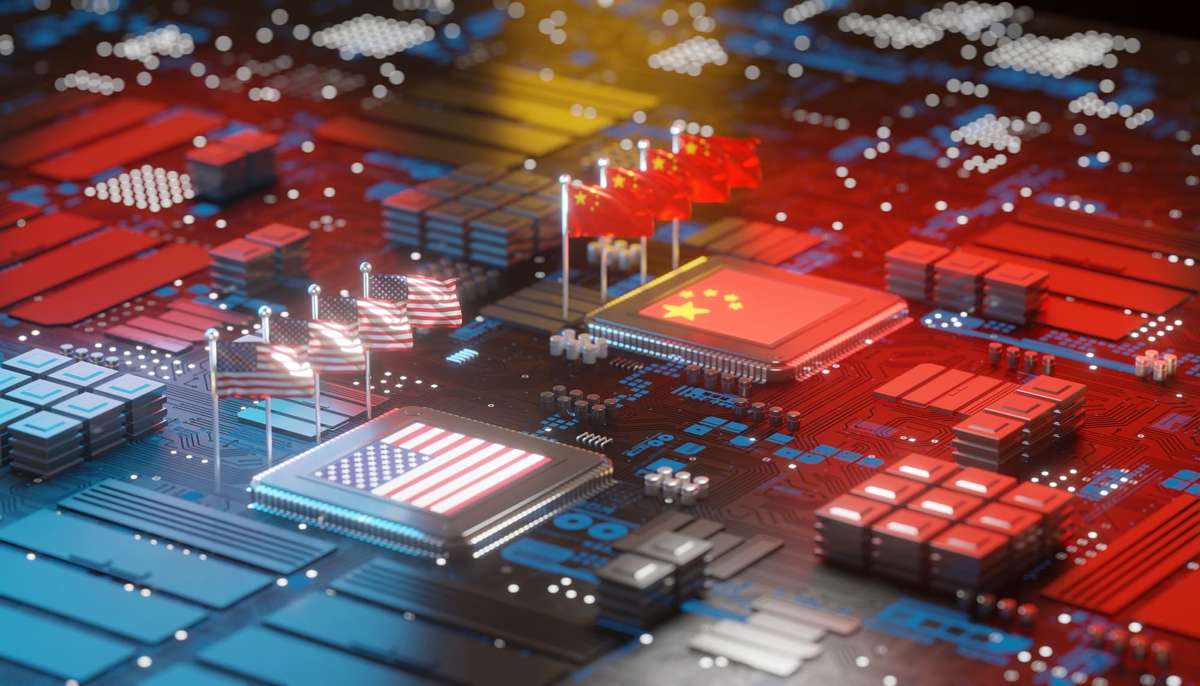世界中に実害をもたらした旧ソ連の原子炉付きレーダー衛星
レーダーという道具は、電波を発射し、対象物で反射してきた反射波を受信して対象物を観測する。この時反射波の強度は、レーダーのアンテナと対象物との距離の4乗に反比例する。
電波の強さは、距離の2乗に反比例して弱くなっていく。その電波が対象物で反射すると、今度は電波は対象物からの距離の2乗に反比例して弱くなっていく。つまりレーダーの送り出す電波と、対象物で反射して帰ってくる電波を比較すると、2乗のそのまた2乗で、距離の4乗に反比例することになるわけだ。
だから、レーダーの送信出力はなるべく大きくしなくてはいけないし、また受信アンテナも大きくて感度が高いものを用意しなくてはいけない。でないと、受信電波が弱くなりすぎて、システムとして成立しなくなる。
レーダーを搭載した衛星の場合、衛星は高度数百kmの軌道から地球表面を照射することになる。この距離で十分な受信波の強度を得るのは、かつてはなかなかの難事だった。
一番単純な解決策は、衛星の軌道高度を低くすることだ。とはいえ、あまり高度を下げすぎると、今度は希薄な上層大気の空気抵抗を受けるので、衛星は短期間で地球に墜落してしまう。
1960年代から80年代にかけて、旧ソ連は、「US-A(Upravlyaemy Sputnik Aktivnyy )」という船舶を監視する軍事用レーダー衛星を、高度250kmという非常に低い高度に打ち上げて運用したことがあった。この高度だと、普通は空気抵抗でじきに衛星が落ちてしまう。そこでソ連は、衛星から大きな空気抵抗を発生する太陽電池パドルを取り去ってしまった。

その代わりに、なんと衛星にウラン燃料を使う原子炉を搭載し、レーダーが必要とする大電力を賄ったのである。RORSATの衛星は寿命が2〜3カ月程度だった。寿命が尽きると、原子炉部分を分離する。分離した原子炉はロケットエンジンで高度800km以上の、空気抵抗がずっと小さな軌道へと送り込まれる。そこで何百年も地球を回っているうちに放射性同位体は半減期を繰り返して消えていき、地球に落下するころには無害になっているという設計だった。
確かに設計の筋は通っている——が、それはトラブルが発生しなければの話だ。1977年9月18日に、打ち上げられたUS-A衛星「コスモス954」は軌道上で故障を起こし、原子炉が分離できなくなった。同衛星は1978年1月24日に大気圏に突入して分解、放射性物質を含む破片は、差し渡し600kmに渡って分散してカナダに落下した。発生した放射性物質汚染の除去作業には大変な手間を要し、カナダは旧ソ連に対して損害賠償を請求。1981年4月、旧ソ連はカナダに対して300万ドルを支払った。
1968年から88年までの20年間に旧ソ連は33機の「US-A」衛星を打ち上げたが、その中には打ち上げに失敗して北大西洋に落ちたものあり、故障で落下寸前に原子炉をなんとか分離して高い軌道に押し込んだものありで、様々な実害を世界に及ぼし続けた。
搭載するものをできるだけ簡素化する「軌道」
強い送信出力と、高感度のアンテナが必要なレーダー衛星は、どのようなものであるべきだろうか。強い送信出力には、大容量の電源が必要になる。旧ソ連のように宇宙用原子炉を利用するのは、危険すぎて論外だ。必然的に、大面積の太陽電池を拡げる必要がある。
加えて、高感度のアンテナは大きくなる。つまりレーダー衛星は、大きなアン��テナと大面積の大陽電池が必須になる。共に、温度変化でたわんだり振動したりする。太陽電池をパドルで拡げて、常に太陽方向を向けるように回転させれば、それもまた姿勢を乱す原因となる。結果、一定の姿勢を保つための姿勢制御装置も大がかりなものとなる。レーダー衛星は、なにかと大仕掛けになりがちなのだ。
これらの問題を解決するために、レーダー衛星は「ドーンダスク軌道(Dawn Dusk Orbit)」という軌道を使うようになった。
地球観測衛星は、地表をなるべく広く観測するために、地球を南北に回る軌道に打ちあげられる。衛星は地球を南北に巡り、地球は東西に自転する。この2つで、地球を南極から北極までスキャンするわけだ。このような軌道を極軌道という。
地球は完全な球ではなく、少し赤道が膨らんだみかんのような形をしている。この影響で、地球を回る衛星の軌道は慣性空間に対して完全に固定したものではなく、少しずつ軌道の向きが変化する。この変化を極軌道でうまく使うと、大陽が当たっている昼の面の上空を飛ぶ時、直下の地方時がいつも一定で、かつ何日かごとに同じ場所の上を通過するという軌道を設計することができる。このような軌道を「太陽同期準回帰軌道」という。
直下の地方時が同じということは、いつどこの上を飛んでも太陽の見える方角は一定ということだ。これは、地表にできる影がいつも同じ方向に出るということであり、光で地表を観測する光学衛星にとっては、得られた画像の分析や比較がやりやすくなるということである。しかも何日か毎に同じ場所の上を通過するので、継続的なデータ取得にも向いている。一��例として、ランドサットシリーズは、回帰日数16日、地方時午前10時の軌道を使っている。この場合、夜の面の上空を飛ぶ時は、直下は午後10時になる。
ドーンダスク軌道は、地方時が午前6時・午後6時の軌道だ。別の言い方をすれば、昼と夜の境目、明暗境界面の上を飛ぶ軌道である。この軌道の特徴は、いつでも大陽が同じ方向に見えるということだ。衛星が地球の影に隠れて夜の空を飛ぶことがないのである。
これは、レーダー衛星にとって大変大きな利点となる。まず、いつでも太陽光が当たるので、電力の心配をする必要がなくなる。センサーが電波を照射するレーダーなので、直下が明るくとも暗くとも関係ない。いつでも大陽が当たって電力が供給されるということは、いつでも地表を観測することができるということである。
しかも、太陽光はいつも同じ方向から入射するので、太陽電池パドルを動かして太陽に向ける必要がない。太陽電池は、太陽光がやって来る方向を向けて衛星本体に固定するだけでよい。余計な駆動機構が不要になるので、姿勢の乱れも発生しない。それだけ姿勢制御装置にかかる負荷も小さくなる。いつも同じ方向から太陽光が当たり続けるので、衛星内部の温度を一定範囲内に保つ熱設計も、非常にやりやすくなる。
ドーンダスク軌道に適合したレーダー衛星は、特徴的な形態となった。典型例はドイツのTerraSAR-X衛星だ。細長い円筒形の本体に、太陽を向けた太陽電池パドルと、地表を向けたレーダーのアンテナが固定してある。どっちも向きを変えるステアリング機構はついていない。要するに茶筒にレーダーアンテナと太陽電池という2枚の「焼き海苔」を張り付けたと思えばいい。極めてシンプルで、故障の発生しにくい優れた設計だ。
もう少し通常の衛星に近い形をしている、イタリアの「Cosmo-SkyMed」衛星も、基本的な考え方は同じだ。地球向きのレーダーアンテナに、太陽を向けた太陽電池パドル。どちらも固定で可動機構はない。
こうして、21世紀に入るころには、ドーンダスク軌道を使うレーダー衛星の“設計の文法”が確立した。
大きなアンテナと大容量のバッテリー。レーダー衛星小型化への2つの障壁
しかし、その一方でレーダー衛星はなかなか小さくはならなかった。1980年代後半から100kg以下の小さな衛星の開発が進み始めた時期、先行したのは光を使って観測する光学衛星だった。特に、1990年代にデジタルカメラの普及と共に受光素子と画像処理の技術が急速に進歩したことから、光学衛星の大幅な小型化が可能になった。極端な話、望遠レンズを付けたデジタル1眼レフカメラを宇宙から地球に向ければ、それは光学衛星となる。2010年代に入ると、米プラネットラボ社のDoveのように数kgの光学衛星が打ち上げられるようになった。

レーダー衛星の小型化に何よりも重要なのは、大電力を必要とするレーダーの小型化だ。
そのためには、2つの技術革新が必要だった。まず、レーダーに使う半導体の技術革新だ。微弱な反射波を確実に受信するためのノイズの小さな受信回路である必要がある。そのためには、低ノイズの受信用半導体の開発が必須だ。また、送信側の電力増幅器も半導体化して、小型軽量と高効率を両立させる必要がある。
次が、電波を送受信するアンテナだ。強い電波を送信し、微弱な反射波を受信する大型のアンテナを開発する必要がある。また、そのアンテナは、小さな衛星に搭載して打ち上げるため、小さく折り畳んで打ち上げ、軌道上で大きく展開する必要がある。宇宙用部品では、可動部位はすべてトラブルの原因だ。途中でひっかかったりすることなく確実に展開し、展開後は十分な精度で形状を維持する——このような構造をどのような材料を使って実現するかは、かなり難しい技術課題である。
加えて宇宙で使える大容量バッテリーも、小型のレーダー衛星には必須だった。小型衛星の場合、打ち上げは、大型の衛星の横に相乗り、あるいは他の小型衛星多数とまとめて行う。つまり、ドーンダスク軌道を使いたくとも、希望した軌道に打ちあげることができるとは限らない。従って、どのような軌道に打ちあげられても機能するように設計する必要がある。
となると、小型衛星にレーダーを積む場合、太陽電池で発生した電力を1度バッテリーに蓄積し、観測�時にはバッテリーからの一気に大電力をレーダーに供給し短時間に狙った特定の場所だけを観測するという設計を行うことになる。大電力を消費するレーダーを動かすには、大容量で一気に大電力を供給できるバッテリーを搭載しなくてはならない。しかもそれは小型衛星に搭載できるぐらい、小さく軽くなくてはならない。
ベンチャー企業の活躍で、人類社会は新たな情報環境へ突入し始めている
これらの課題が解決し、レーダー衛星の民間ベンチャーが立ち上がるようになるのは、2010年代に入ってからのことだった。
2022年夏現在、世界ではレーダー衛星のベンチャーが4社立ち上がっている。フィンランドのICEYE(2014年設立)、アメリカのカペラ・スペース(2016年設立)、日本のシンスペクティブ(2018年設立)、そして日本のQPS研究所(iQPS:2005年設立)だ。iQPSだけ設立時期が早いが、これは小型衛星開発で創業し、途中から小型レーダー衛星の開発に参入したためである。
衛星は、さすがに光学衛星のように数kgまで小さくはならない。4社ともXバンドの比較的周波数の高い電波を使った合成開口レーダー(SAR)を搭載し、分解能1m〜数mを実現した100kg級衛星を開発し、それらの衛星で数十機規模の衛星コンステレーションを構成して地表を観測しようとしている。夜も昼もなく、雲があっても1m分解能でタイミング良く地表を観測し、土地利用や植生の遷移といった長期的な変化だけではなく、土砂崩れや火山噴火による地形の変化、海氷の流れ、船舶の移動や道路の渋滞、駐車場の利用状況など短時間に起きる変化を捉え、その情報を収益化しようとしているわけだ。
もちろん、使用する軌道はドーンダスク軌道だけではない。特にiQPSは、太陽同期準回期軌道ではなく、緯度45度以下の人口密度が高く大都市が集中している領域を対象とした、軌道傾斜角45度の軌道を採用している。
2020年8月現在、ICEYEは21機、カペラは6機、シンスペクティブは2機、iQPSは2機の衛星を軌道上で運用している。衛星機数は今後急速に増える予定だ。シンスペクティブは2026年に30機規模、iQPSは2024年に36機のコンステレーションを完成させるとしている。
このように見てくると、2020年代半ばから2030年代にかけて、人類社会は新たな情報環境へと突入していくことが予想できる。光学とレーダー両方の地球観測衛星コンステレーションが、絶え間なく全地球を観測し続け、その変化を記録していくという環境だ。そうなった暁に、いったい人類社会はどのようなものへと変化していくのだろうか。
すでに前兆と思われる現象は、始まっている。
参照リンク
US-A:https://web.archive.org/web/20070914050635/http://www.astronautix.com/craft/usa.htm
コスモス954号事件外交解決文書(カナダ・ソ連間) :https://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_3/3-2-2-1_j.html
大陽同期準回帰軌道:https://www.restec.or.jp/knowledge/sensing/sensing-2.html
TerraSAR-X:https://www.eoportal.org/satellite-missions/terrasar-x#space-segment
COSMO-SkyMed:https://earth.esa.int/eogateway/missions/cosmo-skymed
ICEYE:https://www.iceye.com/
Capella Space:https://www.capellaspace.com/
Synspetive:https://synspective.com/jp/
iQPS:https://i-qps.net/